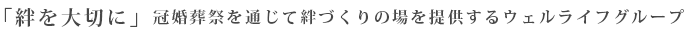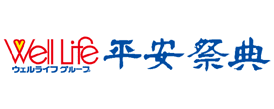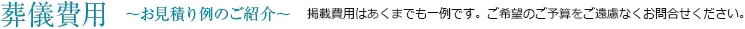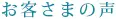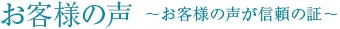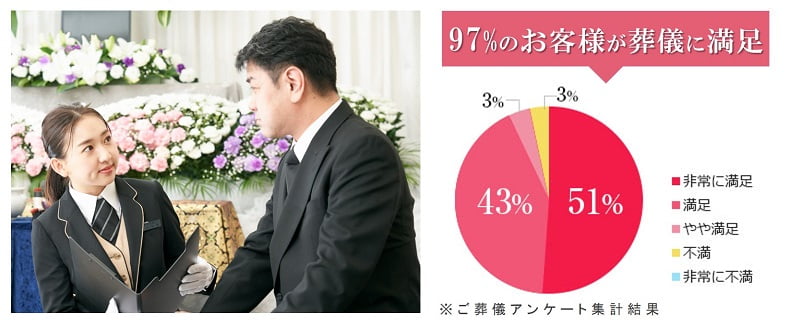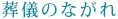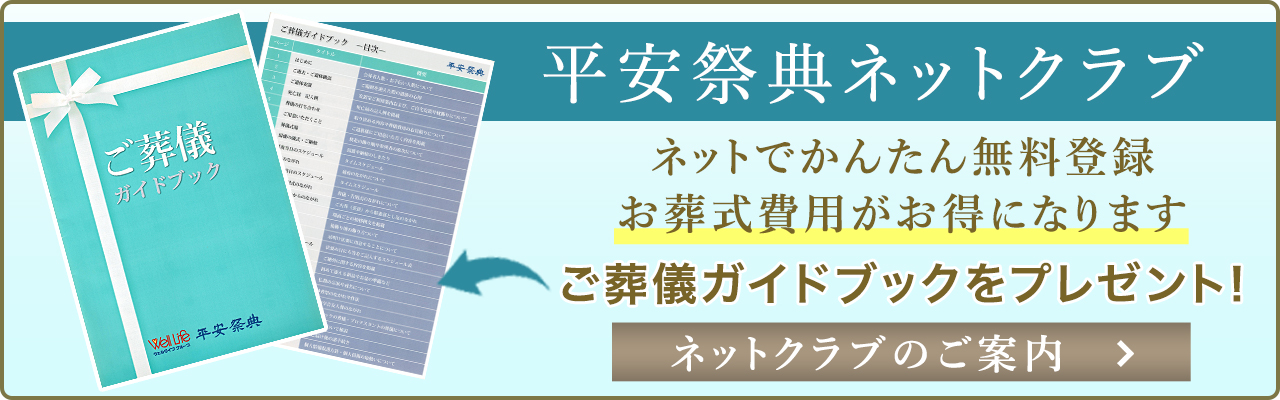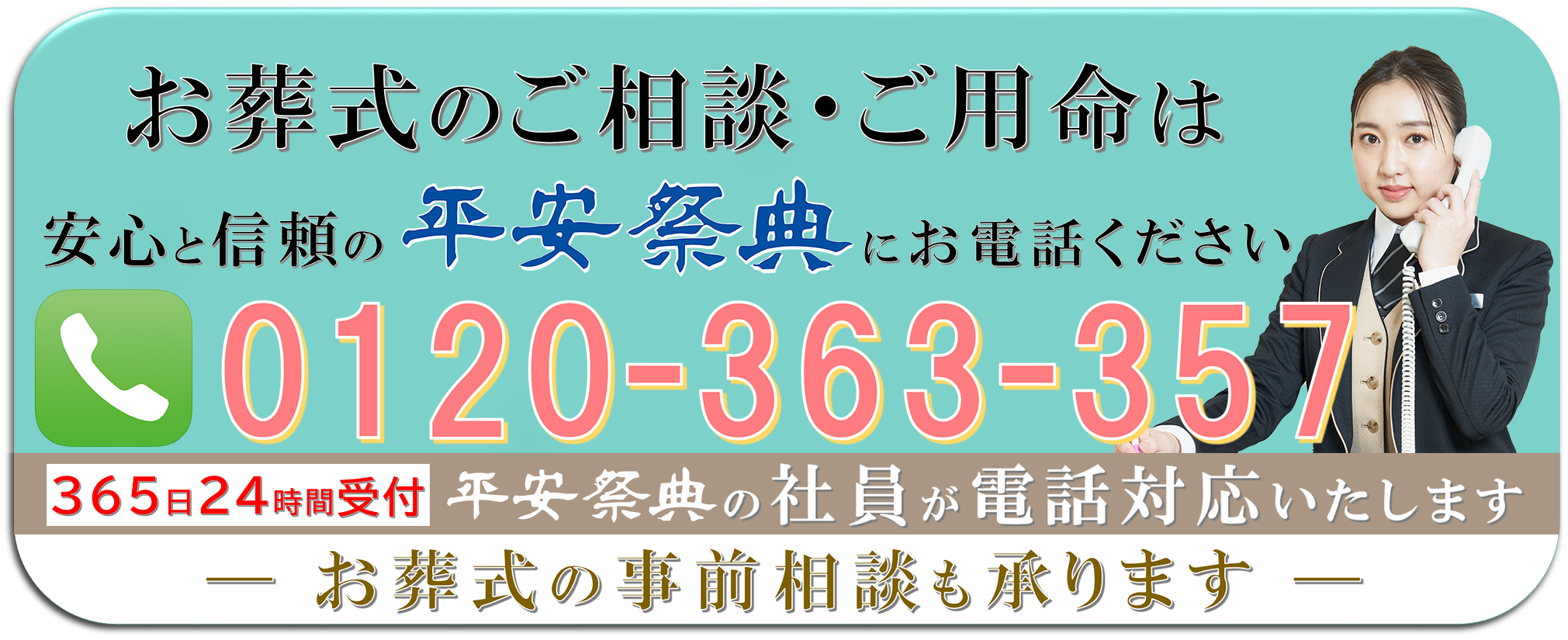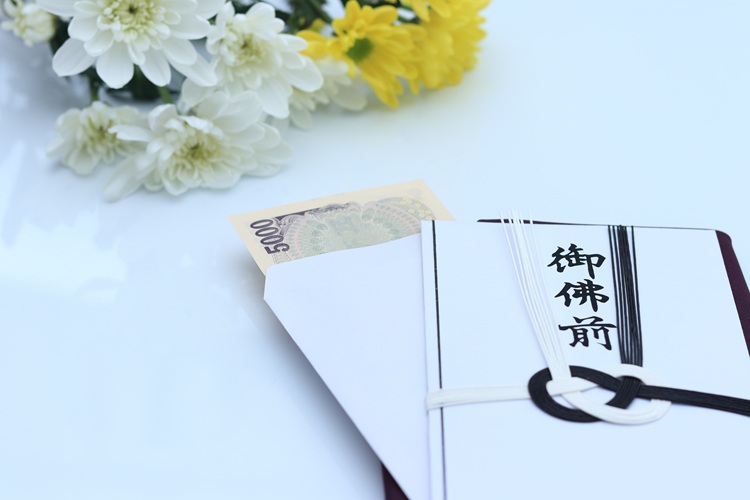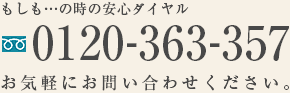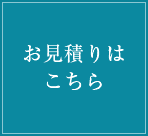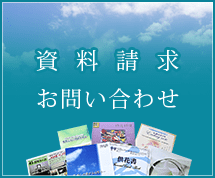マナー
公開日 │ 2025年04月07日
仮通夜とは?本通夜との違いや過ごし方・マナーについて徹底解説
もくじ

1.仮通夜とは故人様がご逝去された日にご遺族のみで執り行うお通夜のこと
仮通夜は、故人様がご逝去された日の夜に執り行い、僧侶や弔問客を招かないのが特徴です。故人様のご自宅で執り行うのが一般的で、特別な儀式はなく、ご遺族のみで最後のお別れの時間を穏やかに過ごします。
仮通夜は通念上、故人様が夜遅い時間にご逝去された場合や、ご親族のご都合上翌日の本通夜に参列するのが難しい場合などに執り行います。仮通夜を執り行わずに、本通夜のみを執り行っても構いません。
2.仮通夜と本通夜の違い
仮通夜と本通夜の違いは、執り行う日程と宗教的な儀式の有無、僧侶や弔問客を招くかどうかにあります。
仮通夜は、故人様がご逝去されたその日の夜に執り行います。故人様のご自宅で執り行うのが一般的で、読経などの宗教的な儀式は執り行いません。僧侶や弔問客も招かず、ご遺族やご親族だけで集まり、故人様を見守りながら静かに過ごします。
本通夜は、故人様がご逝去された日の翌日の夜に執り行います。葬儀場で祭壇を設けて執り行うのが一般的で、僧侶による読経や焼香、喪主による挨拶、通夜振る舞いなど宗教的な儀式を執り行います。僧侶や弔問客を招くため、ご遺族以外の関係者も参列します。
このように、仮通夜と本通夜には日程や内容、参列者の範囲などに違いがあります。仮通夜や本通夜を執り行うかどうかは、故人様の生前のご意向やご逝去された日の状況、ご遺族のご都合やご意向に応じて検討するようにしましょう。
3.仮通夜の過ごし方
仮通夜の意義は、ご遺族のみで故人様を静かに見守り、お別れの時間を共に過ごすことです。宗教的な儀式など、特別なことは行いません。ご自宅でお弁当やオードブルなどを注文し、故人様の傍で食事をしながら思い出などを振り返ります。ただし、宗派や地域によっては、仮通夜でも本通夜のように僧侶を招いて、宗教的な儀式を執り行うことがあります。
4.仮通夜のマナー
仮通夜のマナーは、本通夜と基本的には変わりません。 ただし、参列者の範囲が限定的であることや服装の気遣い、香典の金額の配慮など、マナーとして心得ておくと良いことはいくつかあります。 仮通夜のマナーについて詳しく解説します。
4-1.参列者の範囲
仮通夜に参列するのは、ご遺族やご親族など、故人様と近しい血縁関係にある方々です。 故人様の友人や知人、会社関係者などは参列しないのが一般的です。 故人様のご遺族以外は、翌日に執り行われる本通夜に参列するようにしましょう。
4-2.服装
仮通夜に参列するときの服装では、喪服を着用しないのが一般的です。 紺やグレー、ブラウンなど、控え目な色のスーツやワンピースを着用しましょう。 平服で構いませんが、ジーンズなどカジュアルな服装は避けるのがマナーです。
4-3.香典の金額
仮通夜の香典の金額相場は、本通夜に参列する場合と同じく、故人様との関係性で変動します。 故人様が父母の場合は10万円、ご兄弟の場合は5万円、その他の親類は1万円が目安相場です。
出典:「香典をいくら包めばいいの?」(一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会) (https://www.zengokyo.or.jp/manner/funeral/f08/344/)
ただし、本通夜に参列する場合は、仮通夜では香典を持参しないのが一般的です。 香典を複数回渡すことはマナー違反となるため、本通夜あるいか仮通夜のどちらかで渡すようにします。 仮通夜に手ぶらで参列するのが憚れる場合は、お供え物として線香や菓子折りなどを持参すると良いでしょう。
5.仮通夜を執り行うケース・執り行わないケース
仮通夜は、必ずしも執り行わなくてはならないわけではありません。 故人様がご逝去された時間帯やご遺族のご都合などに応じて、判断するようにしましょう。仮通夜を執り行うケース・執り行わないケースについて詳しく解説します。
5-1.仮通夜を執り行うケース
仮通夜を執り行う一般的なケースは、故人様が夜遅い時間にご逝去された場合や、ご遺族がご都合上本通夜に参列できない場合などです。故人様が夜遅い時間にご逝去された場合、本通夜の準備が間に合わない可能性が高く、ご遺族の気持ちの整理にも時間を要することから、ひとまず仮通夜を執り行うことが多いようです。
ご遺族が仕事のご都合などで翌日の本通夜に参列するのが難しい場合も、仮通夜を執り行うことがあります。 葬儀場が休みであったり、火葬場の予約がすぐに取れなかったりする場合も、葬儀の日程を調整するために仮通夜を執り行うことがあります。 仮通夜に特別な準備は必要ないため、故人様とのお別れの時間をご遺族だけで穏やかに過ごしたいという想いから、執り行うこともあります。
5-2.仮通夜を執り行わないケース
仮通夜を執り行わないケースは、故人様が病院でご逝去されたために、ご自宅には帰らない場合などです。 病院でご逝去されると、ご遺体はご自宅には運ばれず、葬儀社の安置所などに預けられます。仮通夜はご遺族が故人様を見守り共に過ごすことが意義であることから、直接安置所に預けられる場合は、執り行うことが基本的にはできません。
お通夜自体を執り行わない「一日葬」などの場合も、仮通夜は執り行わないのが一般的です。 仮通夜を執り行うかどうかは、宗派や地域の慣習にもよります。 仮通夜や本通夜を執り行わなくても、ご遺族が話し合って決定したことであれば、問題ございません。
仮通夜はご遺族だけで故人様を偲ぶための大切な儀式(まとめ)
仮通夜は本通夜の前日の夜、つまり故人様がご逝去されたその日に執り行うお通夜のことです。仮通夜は本通夜とは異なり、僧侶や参列者を招かず、ご遺族のみで執り行います。読経や焼香など、宗教的な儀式を執り行わないのが一般的です。
仮通夜のマナーは、本通夜の礼儀と基本的には変わりません。参列者はご遺族やご親族のみとなるため、喪服は着用せず控えめな平服にし、香典は本通夜や葬儀に参列できない場合のみ渡すようにします。
仮通夜の意義は、宗教的な儀式ではなく、ご遺族が故人様を見守り最後のお別れの時間を共に過ごすことにあります。必ずしも執り行う必要はありませんが、ご遺族でよく話し合い、葬儀の日程なども考慮したうえで判断するようにしましょう。