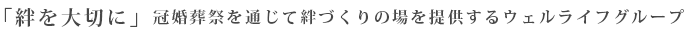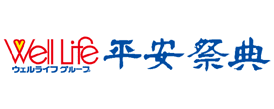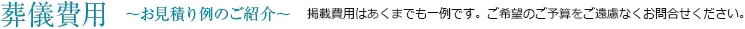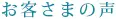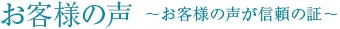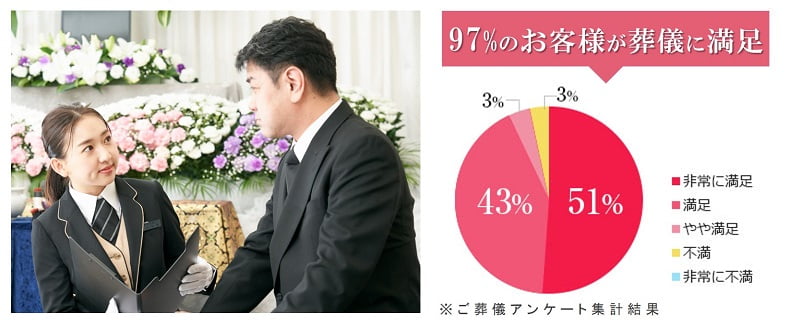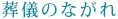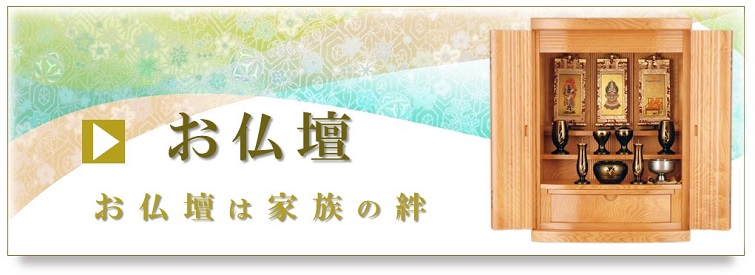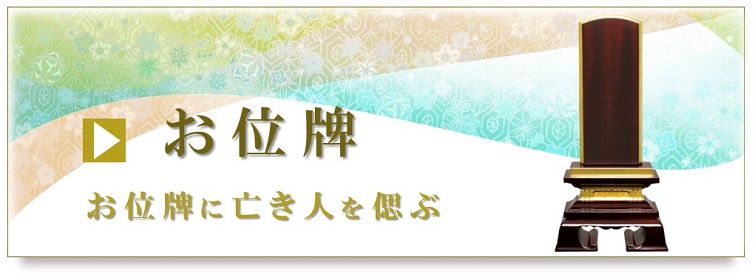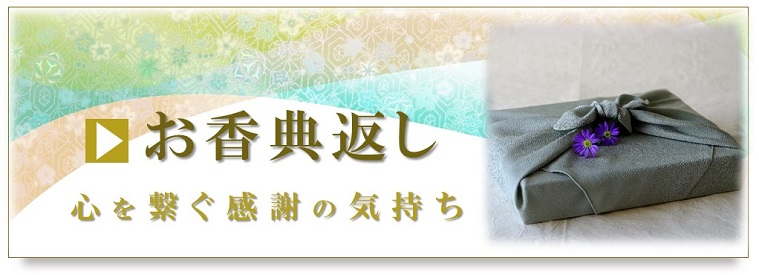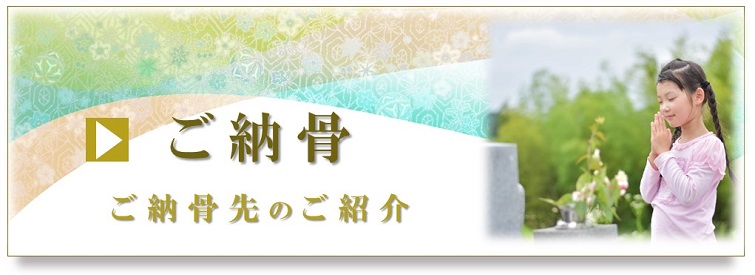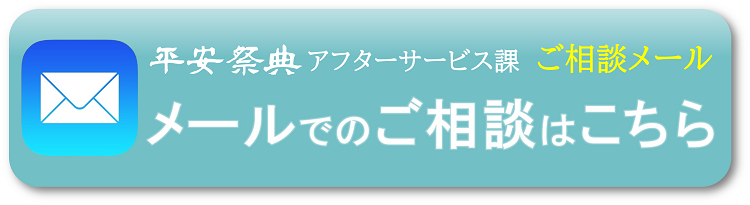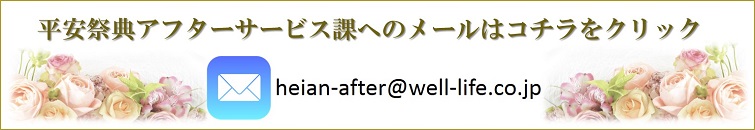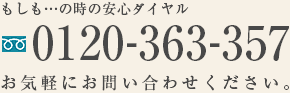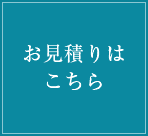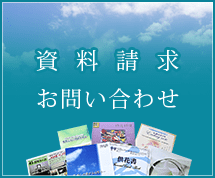ご葬儀後のアフターサービス
新着情報[ お仏壇 ]特価セール
アクセス
仏壇仏具の専門店
東京都江東区の亀戸駅から徒歩4分
仏壇仏具の専門店[平安祭典アフターサービス課]には、多様化するご供養ニーズにお応えした、豊富な供養と癒しの商品をご用意いたしております。

お仏壇・お位牌
ご供養をアフターサービス
お困り事のお役に立ちます

ご相談受付
ご納骨

ご納骨について
ご納骨は、忌明けとなる四十九日法要と合わせて行うのが一般的ですが、ご納骨先がすぐに決まらない場合は、百ヵ日法要や一周忌法要まで、ご自宅で供養するご家庭もあります。また、寺院や霊園の納骨堂などに一時的に預けることも出来ます。
墓地について
墓地は買うのではなく、永代使用料を支払って借り受けるものです。そのため、固定資産税は掛かりません。永代使用権は子孫に継承できますが、第三者への転売はできません。墓所によっては、管理費がかかる所もあります。
埋葬について
埋葬するには「埋葬許可証」が必要です。火葬許可証に火葬場で火葬したという証明印が押されたものが埋葬許可証となります。納骨時に墓地・霊園の場合は管理者に、お寺の場合は住職に預けます。

―墓地霊園ご紹介―
お墓やご納骨も、お気軽に平安祭典アフターサービス課にご相談ください。
大切な故人様の御遺骨をお納めするお墓は、ご家族がご供養にお参りしやすい場所が理想的ですが、都心部では費用も高額なため、納骨先が決まっていないご家族は悩まれることでしょう。
平安祭典アフターサービス課では、経験豊富なスタッフが、ご要望にそった寺院・霊園・納骨堂・海洋散骨などをご提案させていただきます。
法事・法要
―功徳となる追善供養―
お葬式の後も、様々なご供養がございます。平安祭典アフターサービス課は、施主様のささえとなり、お役に立つアフターサービスをご提供いたしております。
法事・法要のことは、平安祭典アフターサービス課にご相談下さい。

法要 ほうよう
法要とは、僧侶にお経を読んで頂き、追善供養することをと言います。
法事 ほうじ
法事とは、法要後に会食・お斎(おとき)まで行うことを言います。
仏教では、七日ごとに法要を行なうとされていますが、葬儀に合わせ繰上げ初七日法要をおこなった後に僧侶を招いて読経供養を施すのは、忌明けの四十九日法要。次は100ヵ日法要を行なうご家庭が多いようです。
年忌法要とは、故人を偲び追善供養を行う事で、死後満一年目に一周忌を執り行います。
翌年の二年を三回忌とし、この法要までは、ご遺族は喪服着用で供養される方が多いようです。
その後は死亡年を含めて数え、七年目に七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌まで営むのが一般的です。
以降は五十回忌、百回忌となり、その後は五十年目ごとに法要を営みます。
浄土真宗および真宗系の宗派では、臨終と同時に極楽往生する往生即成仏の教えがあり、中陰法要の意味は、故人を偲び、仏法に接する機会とされています。
新盆・お盆
―大切な人をお迎え―

故人が亡くなられてから、初めて迎えるお盆が「新盆」です。
新盆(にいぼん)初盆(はつぼん)とは、同じ意味の言葉です。忌明けとなる四十九日を過ぎてから、初めて迎えるお盆のことを言います。
お盆には、亡くなった人が年に一度、お家に帰ってくるという言い伝えもあり、亡くなった家族やご先祖様を敬い感謝する、大切な伝統行事です。
ご自宅に精霊棚(しょうりょうだな)をお飾りし、僧侶を招き、棚経(たなぎょう)と言われる盂蘭盆棚経(うらぼんたなぎょう)のお経をあげて頂きます。
ご家族を亡くされて初めて迎える新盆は、準備や手順が分からず、お困りになられるご家庭が多いようです。
平安祭典アフターサービス課では、新盆セット・お盆セットのご注文を頂いたご家庭へ、ご供養の専門知識を持ったスタッフによる、配送サービスと精霊棚飾りの設営サービスを行なっております。
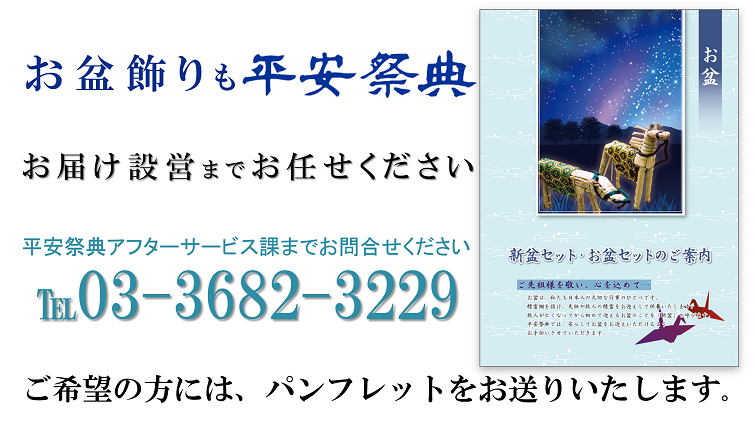
四十九日の忌明け前にお盆となる場合
忌明けとなる四十九日前にお盆を迎える故人様は、翌年が初盆(新盆)となります。
ご先祖様を敬う大切な行事[お盆]
東京都では7月にお盆を迎えますが、地方では8月にお盆を迎えるなど地域によって時期が違います。お盆には「新のお盆」と「旧のお盆」と二通りの時期があるからです。
お盆を迎える月の13日~16日の間は、仏壇のあるお部屋に精霊棚(しょうれいだな)飾りを施し、ご先祖様や亡くなられた家族の霊をお迎えいたしましょう。
真心のアフターサービス
― ご供養をサポート ―
平安祭典アフターサービス課は、お客様に寄り添い、ご満足頂けるサポートサービスをご提供致します。ご供養に関することは、平安祭典アフターサービス課にご相談ください。