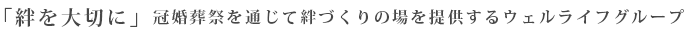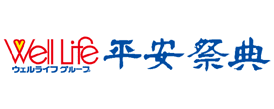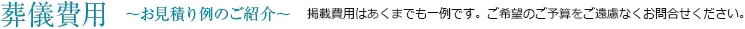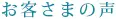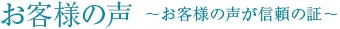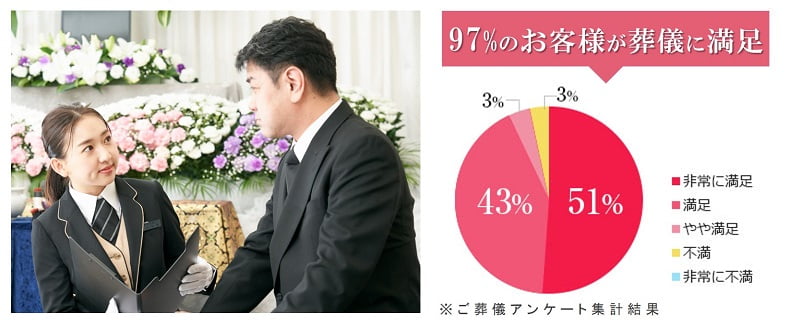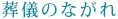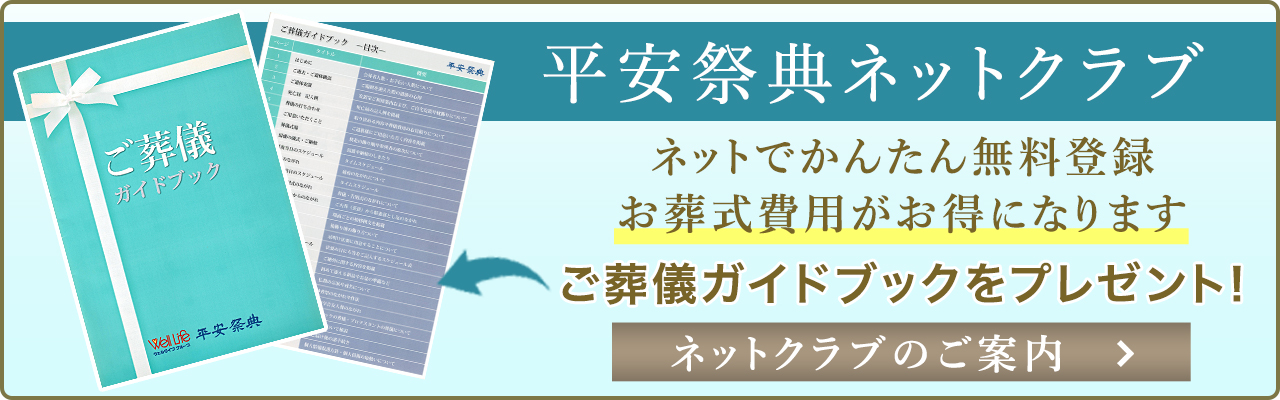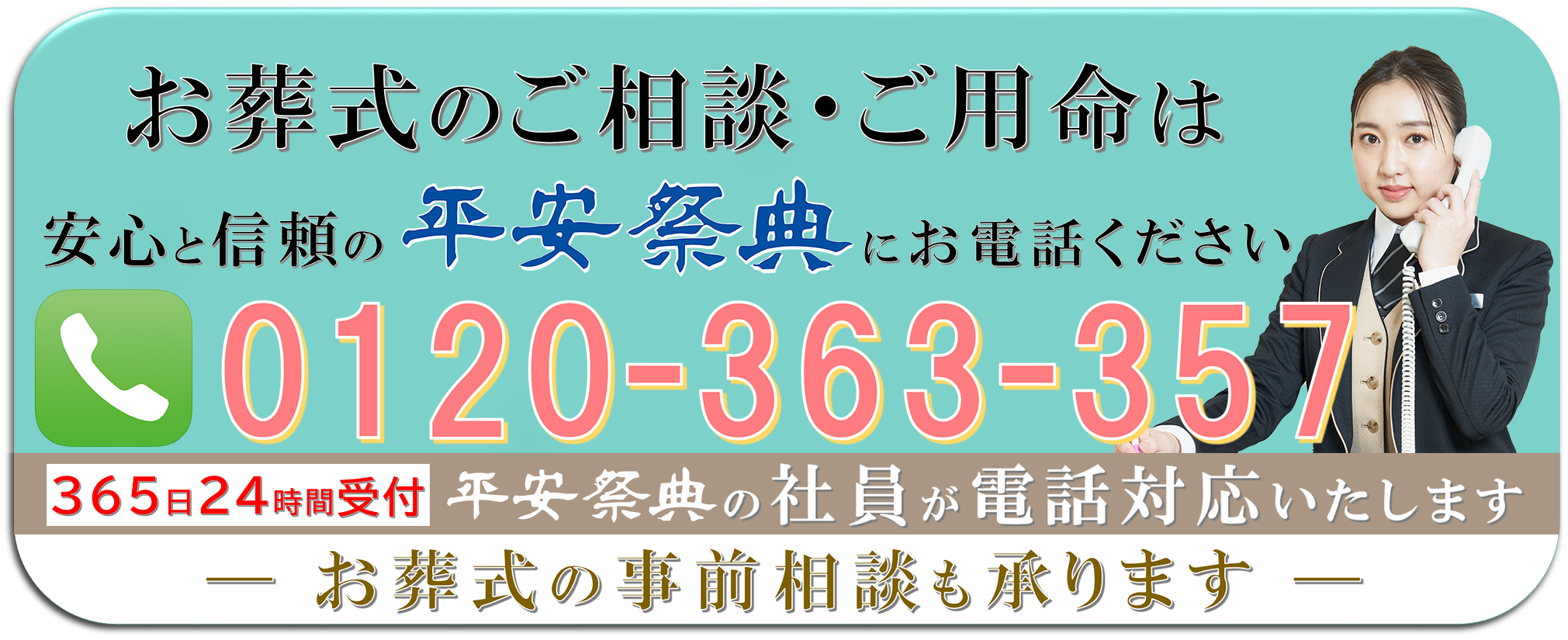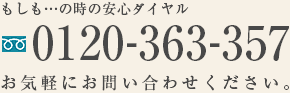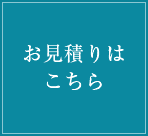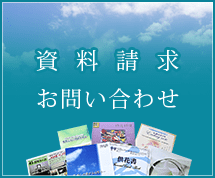マナー
公開日 │ 2024年05月31日
更新日 │ 2024年06月10日
弔問とは?基本的な流れと弔問マナーについて詳しく解説
もくじ
1.弔問(ちょうもん)とは?
2.基本的な弔問の流れ(ご自宅の場合)
2-1.予め自宅へ訪問の許可を頂く
2-2.お悔やみの言葉を述べる
2-3.お線香や供物を手向ける
3.基本的な弔問の流れ(式に参列する場合)
3-1.式場内で香典を渡す
3-2.お悔やみの言葉を述べる
3-3.式中に焼香を済ませる
4.弔問する際のマナーについて
4-1.弔問の可否を予め確認する
4-2.長居することは避ける
4-3.服装は状況に応じたものを着用する
4-4.忌み言葉や重ね言葉を使わない
4-5.自宅への弔問時は香典を渡さない
弔問は身近な方の訃報を聞きつけて、遺族のもとへお悔やみを述べに伺うことです(まとめ)

そうした流れを理解しておくのはもちろんのこと、訪問する際に気をつけるべき点や服装などの弔問マナーもしっかりと抑えておく必要があるでしょう。
弔問する際には大切な方を亡くされて辛い心境にあるご遺族を気遣い、失礼のない振る舞いをすることが大切です。
そこで今回は弔問に関する内容について、実際の流れから状況に応じた弔問マナーに至るまでを解説いたします。身近な方の訃報はいつ、どのタイミングで知らされるか分からないため、事前に内容を確認しておくようにしましょう。
1.弔問(ちょうもん)とは?
弔問とは身近な方の訃報を聞きつけて、遺族のもとへお悔やみを述べに伺うことです。伺う場所は故人の安置されている自宅などを指すことが多いですが、通夜や葬儀・告別式の執り行われる式場を指す場合もあります。
なお、式場へ伺う際は「会葬する」「参列する」という表現も使用されます。自宅と式場のいずれの場合においても、予め弔問する際の基本的な流れやマナーを知った上で、失礼のないような振る舞いを心がける必要があるため、それぞれ順に見ていきましょう。
2.基本的な弔問の流れ(ご自宅の場合)

故人が自宅に安置されている場合には、式への参列と流れが異なるため注意が必要です。また、亡くなって間もないため、家族は葬儀の準備で慌ただしいことも多く、心情に配慮した対応が求められます。
ここでは、自宅へ弔問する際の基本的な流れについてご紹介いたします。
2-1.予め自宅へ訪問の許可を頂く
訃報を受けた際に、親しい間柄であれば直接会いたいと思う方も多いでしょう。しかし、訪問はご遺族にとって負担になる場合もあります。たとえ親しい間柄であっても、事前に家族へ連絡を取り、自宅訪問の許可を得てから伺うようにしましょう。
2-2.お悔やみの言葉を述べる
玄関先でお迎えいただいた際に、まずはその場で心からのお悔やみの言葉を述べます
その場合、特別な言い回しなどはせず
- この度は誠にご愁傷様です
- 謹んでお悔やみ申し上げます
といった言葉を短く伝えるだけで十分です。その後、家族から故人との対面やお参りを案内されてから自宅へ上がらせてもらうようにしましょう。
2-3.お線香や供物を手向ける
故人の安置されている部屋でお線香をあげ、供物やお花を持参している場合は、家族に断ってから供えます。お顔を拝見する際も家族に声を掛けてから対面し、亡くなった要因などを詳しく尋ねることは避けましょう。もし言葉を掛けるとすれば「安らかなお顔をされてますね」といった程度の言葉に留めておくようにします。
3.基本的な弔問の流れ(式に参列する場合)
最近では住宅事情の兼ね合いや、気持ちの面での負担から故人が自宅にいない場合もあるため、その際は自宅ではなく通夜や告別式の日に式場へ参列をして対面する流れとなります。
ここからは実際に式場に到着してからの弔問の流れについて具体的に見ていきましょう。
3-1.式場内で香典を渡す

式場に入るとすぐに受付が設置されていることが多いです。その場で香典を渡し、受付が無ければ喪主に直接渡しても問題ありません。
また、家族側としては香典を受け取った方へのお返しなどが用意されていることが多いため、後から見返して分かるように香典袋には名前や住所、連絡先といった情報を記載しておくことも大切です。
3-2.お悔やみの言葉を述べる
自宅へ弔問するのと同様に、式に参列して家族とお会いした際にはまずお悔やみの言葉を述べます。ただし、家族が他の方との挨拶をされていたり、式前の準備で慌ただしくされていたりすることもあります。
その場合には無理に声を掛けることはせず、式が終わった後など落ち着いた頃合いを見てお悔やみを伝えるようにしましょう。
3-3.式中に焼香を済ませる
式が始まると順にお焼香の案内が入ります。先に遺族や親戚が案内されてから、一般の参列者の案内となるので、心を込めてお焼香を済ませるようにします。
親族は式が終わるまで式場内で着席をしたままですが、一般の参列者の方の場合は退出をして別室のお清めの席へと案内されます。お清めで通夜振る舞いの食事が用意されている場合には、短い時間でも構わないのでなるべく立ち寄るようにしましょう。
4.弔問する際のマナーについて
弔問する際はご遺族に対して失礼のないような振る舞いを心掛ける必要があります。あらかじめ抑えておきたい大切なマナーについて5つご紹介します。
4-1.弔問の可否を予め確認する
弔問する際は予め遺族へ日時を伝え、弔問の許可を取っておくことが大切です。特に自宅への弔問となる場合は、お迎えする準備などもあるため、連絡無しにいきなり訪問されると、相手方の大きな負担となってしまいます。
また、式に参列する場合においても、最近では親族を中心とした家族葬で執り行っていることが多く、予想外の参列者が来られた際に慌ててしまう可能性もあるため、事前の連絡は必要です。
4-2.長居することは避ける
自宅や式場へ弔問した時は、長居を避けるのがマナーです。なぜなら、ご遺族にとっては気を遣うことが負担になる場合があるからです。ただし、故人との思い出話が慰めになることもあるため、遺族から求められた場合は少しの間お話しすることも考慮しましょう。
4-3.服装は状況に応じたものを着用する
自宅に弔問する際の服装は基本的に平服で構いません。ただし、派手な色合いや目立つアクセサリーなどの装飾は避けるようにしましょう。通夜や告別式に弔問する際は、一般的な喪服を着用して伺います。
4-4.忌み言葉や重ね言葉を使わない
弔問してお悔やみの言葉を述べる際には、下記のような忌み言葉や重ね言葉を使うことはマナー違反となるため避けましょう。
- (忌み言葉)「死ぬ」「生きる」「別れる」「終わる」「逝く」「切れる」「消える」「苦しむ」
- (重ね言葉)「重ね重ね」「わざわざ」「再三」「いよいよ」「たびたび」「くれぐれも」「返す返す」「続いて」
4-5.自宅への弔問時は香典を渡さない
自宅への弔問時に香典を持参することは、事前に準備していたとみなされるため、控えましょう。香典は通夜や告別式に参列する際に持参し、参列できない場合は式後のタイミングでご遺族に渡すようにします。
弔問は身近な方の訃報を聞きつけて、遺族のもとへお悔やみを述べに伺うことです(まとめ)
身近な方の訃報を聞いて弔問する際は、自身の都合で伺う日時や場所を決めるといった行為はマナー違反となります。そのため、どんなに親しい仲であった方でも、先ずは遺族へ直接連絡を取って弔問の可否を確認することが大切です。
最近では葬儀を近しい方だけで執り行う家族葬が増えてきていることもあり、式場への弔問を遠慮されるケースもあります。
その場合にはご自宅へ直接弔問に伺うことも考慮し、遺族の心情や体力に配慮した対応を心掛けましょう。
実際に訪問した際は決して長居することなく、まずはお悔やみの気持ちを適切に伝えることを意識します。