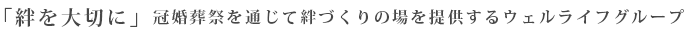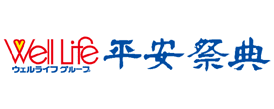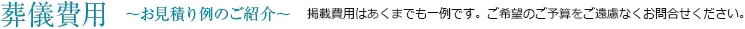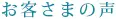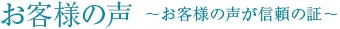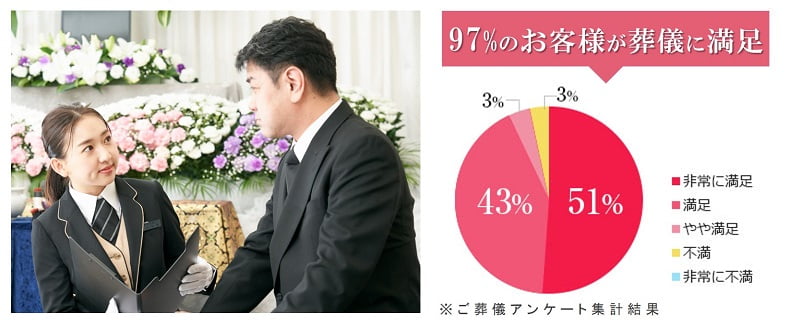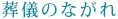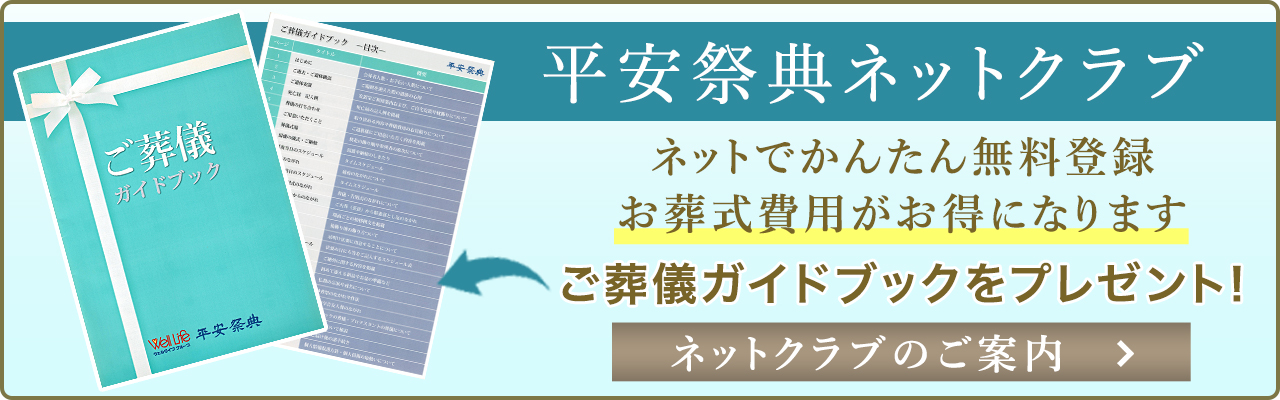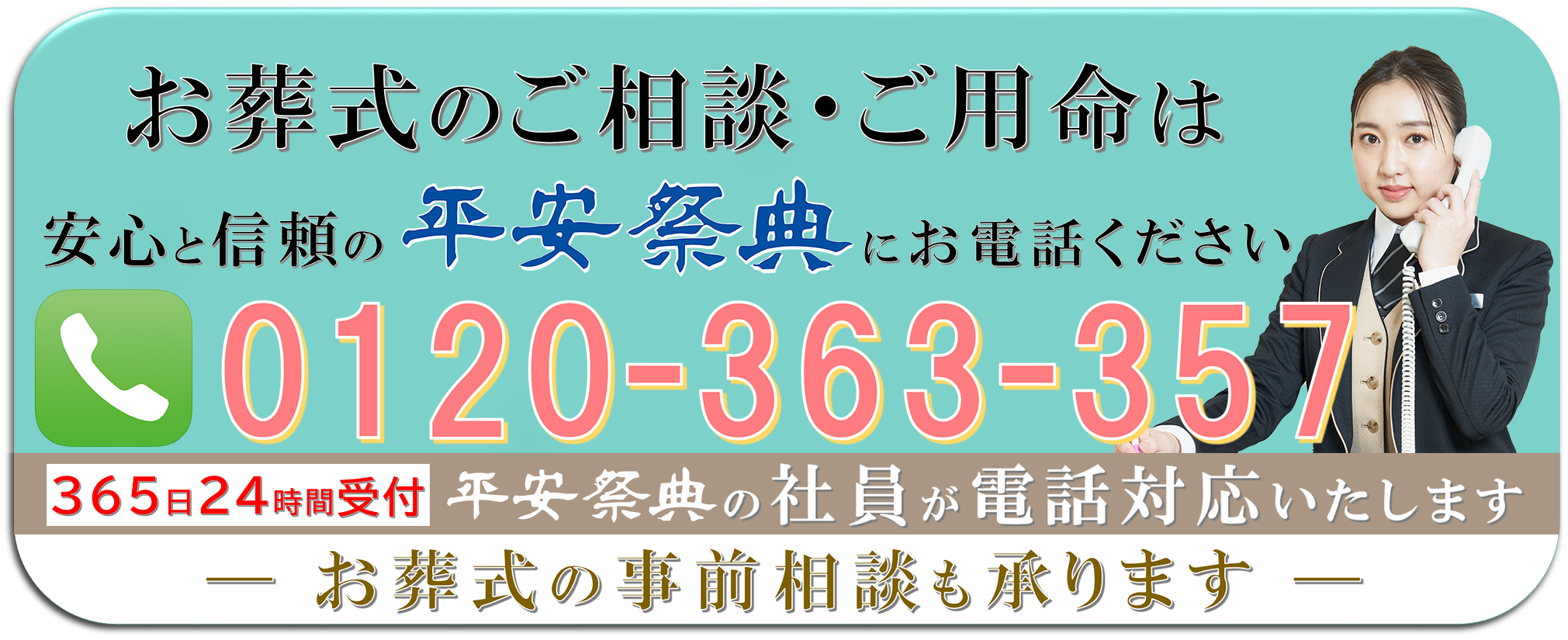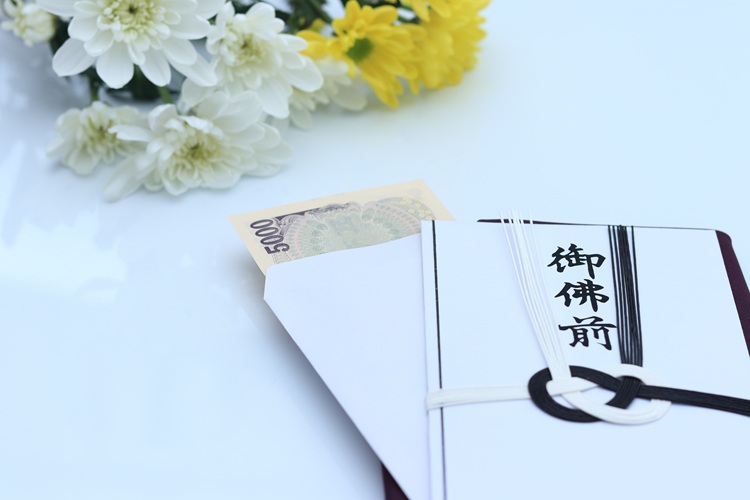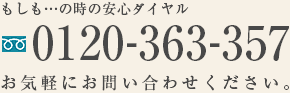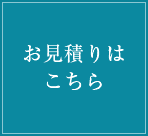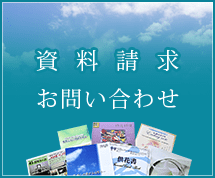知識
公開日 │ 2025年09月26日
位牌の文字入れは自分でできる?何を書くの?注意点まで徹底解説
もくじ

1.位牌の文字入れとは
位牌の文字入れとは、本位牌に故人様の戒名や没年月日などの情報を書き入れることです。文字入れの方法は宗派や地域によって異なりますが、故人様が安らかに成仏し、ご遺族が日々手を合わせるための心の拠り所となるよう、丁寧に仕上げる必要があります。位牌の文字入れには、故人様の生きた証を後世に残すという意味合いも含まれています。
1-1. 位牌の文字入れは自分ではしないのが一般的
位牌の文字入れは自分でもできますが、一般的には葬儀社や菩提寺に依頼します。位牌に文字入れする作業には、高い技術が求められます。 ご自分で文字入れをすると、文字が滲んだり全体のバランスが乱れてしまったり、納得のいかない仕上がりになってしまう可能性があります。
位牌の文字入れの修正は難しいため、納得のいかない仕上がりになってしまった場合は、新たに注文をし直す必要があります。
故人様の戒名や俗名といった大切な情報を正確に、美しく刻むためには、専門の技術を持つ葬儀社や菩提寺に依頼することを推奨いたします。
2.位牌の文字入れで書き入れること
位牌の文字入れでは、梵字・戒名・没年月日・俗名・没年齢などを書き入れます。依頼する際には、確かな情報を伝えられるよう準備を進めましょう。位牌の文字入れで書き入れることを詳しく紹介します。
2-1.梵字(ぼんじ)
梵字とは、古代インドの言葉「サンスクリット語」を書き表すための文字のことです。 仏教では、仏様や菩薩様を象徴する一文字として用いられています。 位牌には、戒名の上に梵字を書き入れるのが一般的です。 梵字を書き入れることで、故人様が仏様の弟子となったことを表せるからです。
位牌に書き入れる梵字は、宗派によって異なります。 たとえば、真言宗・天台宗では大日如来を象徴する「ア」の梵字を、浄土宗では阿弥陀如来を象徴する「キリーク」の梵字を書き入れるのが一般的です。日蓮宗や曹洞宗など、梵字を用いない宗派もあります。 位牌の文字入れを依頼する際は、故人様の宗派の慣習を事前に確認することが大切です。
2-2.戒名(かいみょう)
戒名とは、故人様が仏様の弟子になった証として授けられるお名前のことです。 戒名には位があり、生前の信仰やご功績に応じて、菩提寺の僧侶に授けていただきます。戒名は、「院号」・「道号」・「戒名」・「位号」の4つで構成されています。それぞれを組み合わせて、「○○院△△居士」や「○○院△△大姉」などと表記されます。 戒名は、故人様の魂が位牌に宿るための、最も重要な情報です。
2-3.没年月日
没年月日とは、故人様がご逝去された年月日のことです。宗派や地域の慣習によって、位牌の表か裏、どちらかに書き入れます。
白木位牌には、没年月日の前後に「没」や「寂」が記されていることがありますが、本位牌では省略するのが一般的です。没年月日は、故人様の旅立ちの日を永遠に記録する、大切な情報となります。
2-4.俗名
俗名とは、故人様の生前のお名前のことです。
戒名がある場合は、位牌の裏面に書き入れるのが一般的です。 実は、位牌は戒名がなくても作ることができます。戒名がない場合は、俗名を表面に書き入れ、お名前の下に「之霊位」と記します。俗名を記すことで、ご遺族がより身近に故人様の存在を感じられるでしょう。
2-5.没年齢
没年齢は、故人様がご逝去された年齢のことです。没年齢は、数え年か満年齢で記されます。 どちらで記載するかは宗派や地域の慣習によって異なりますが、一般的には享年(きょうねん)あるいは行年(ぎょうねん)という言葉を添えて書き入れられます。
享年は天から授かった年数のことで数え年で表し、行年は何歳まで生きて修行したかという期間のことで満年齢で表されます。 近年では、満年齢を基準とする行年を用いることが多くなっています。
3.位牌の文字入れの方法

位牌の文字入れの方法には、機械彫りと手書きがあります。 機械彫りは文字の輪郭がはっきりしやすく、手書きは柔らかい印象に仕上がる特性があります。 位牌の文字入れの方法を詳しく解説します。
3-1.機械彫り
位牌の機械彫りは、専用の彫刻機を使って文字を彫る方法です。機械で彫るため、文字の輪郭がはっきりとしており、均一で美しい仕上がりになります。耐久性が高く、作業時間を長く要さないため、納品までの期間が短いのが特徴です。
3-2.手書き
位牌の手書きは、職人が筆と漆を使って、一つひとつの文字を手で書き入れる方法です。手書きであるため、文字に柔らかさや温かみがあり、職人の個性や技術が反映されます。ただし、手書きの位牌は機械彫りと比較すると、耐久性がやや劣る傾向にあります。伝統的で格式高い印象に仕上がりますが、納品までにはある程度の期間を要する点に留意しましょう。
4.位牌の文字入れのお布施
位牌の文字入れを依頼する際には、お布施が必要となります。位牌のお布施は、文字入れの作業に対する感謝の気持ちとして、葬儀社や僧侶にお渡しする金銭のことです。お布施の金額に、明確な相場はございません。宗派や地域の慣習、菩提寺との関係性によっても異なるため、不安な場合は事前に確認しましょう。
5.位牌の文字入れの期間目安
位牌の文字入れの依頼から納品までは、約2週間ほどの期間を要します。位牌は、四十九日法要までに用意するのが一般的です。四十九日法要では、仮の位牌である白木位牌から、永代にわたりお祀りする本位牌に故人様の魂を移し替える「魂入れ(開眼供養)」の儀式を執り行います。魂入れの儀に間に合わせるためにも、葬儀を終えたらできる限り早く、位牌の文字入れの準備を始めましょう。
6.位牌の文字入れをするときの注意点
位牌の文字入れをするときの注意点は、文字色を決めておくことです。 文字のレイアウトに配慮することも、忘れないようにしましょう。位牌の文字入れをするときの注意点を詳しく解説します。
6-1.文字色を決めておく
位牌の文字色は、金色が主流です。しかし、宗派や地域の慣習によっては、白色や朱色などが使われることもあります。
ご先祖様の位牌がある場合は、統一感を出すために、同じ文字色にすることもあります。位牌の色合いによっても適切な文字色は異なるため、悩まれた際は葬儀社にご相談することを推奨いたします。
6-2.レイアウトに配慮する
位牌の文字入れでは、戒名や俗名、没年月日などのレイアウトに配慮することも重要です。故人様の大切な情報をそれぞれどのような配置で、どのくらいの大きさで記すかによって、位牌の印象は大きく変わります。ご先祖様の位牌がある場合は、仏壇全体のバランスも考慮しましょう。
位牌の文字入れは葬儀社や菩提寺に依頼しましょう(まとめ)
位牌の文字入れは、故人様の魂が宿る大切な仏具を完成させるための重要な作業です。位牌は、故人様への想いを形にするものです。ご自身で文字入れを行うよりも、専門の技術を持つ葬儀社や菩提寺に依頼することを推奨いたします。梵字や戒名、没年月日、俗名といった故人様の情報を正確に、かつ美しく刻んでもらうことが、後悔のない位牌選びにつながるでしょう。
位牌の文字入れの方法には機械彫りと手書きがあり、納品までには約2週間ほどの期間を要します。四十九日法要に間に合わせるためにも、葬儀後はできるだけ早く準備を始めましょう。