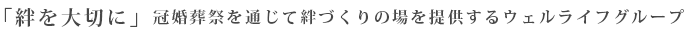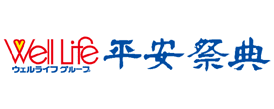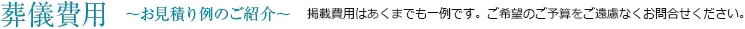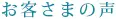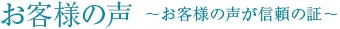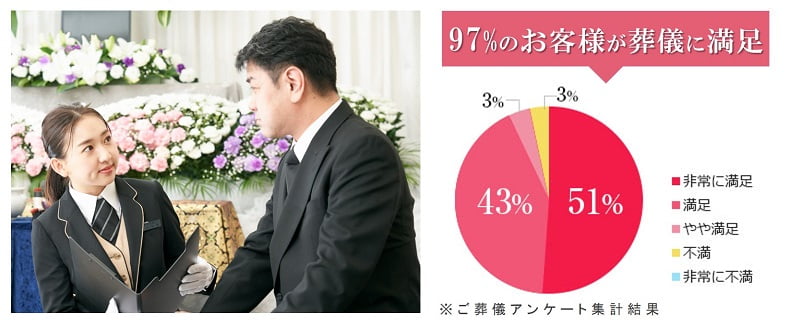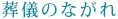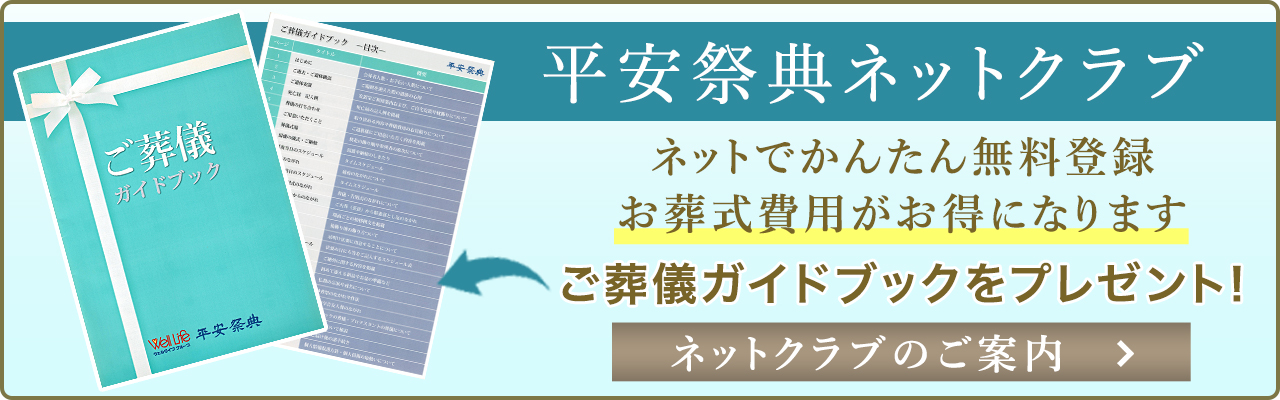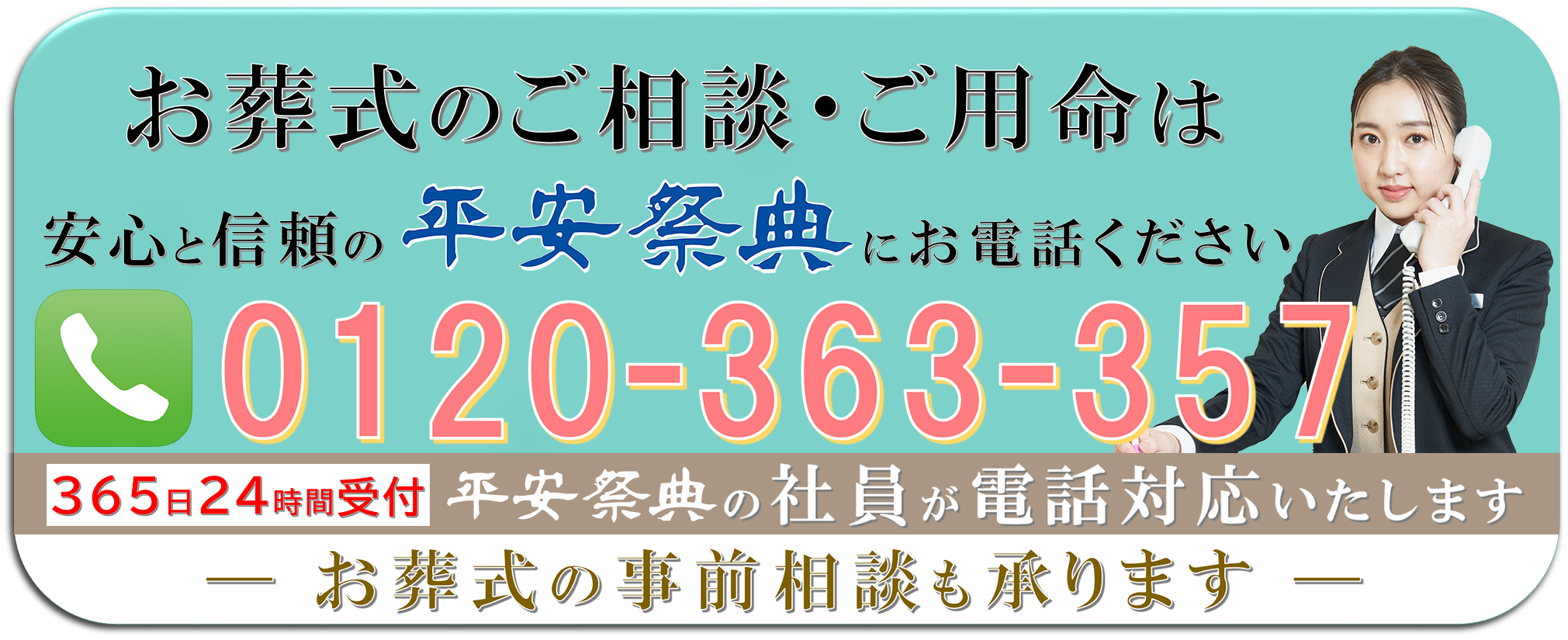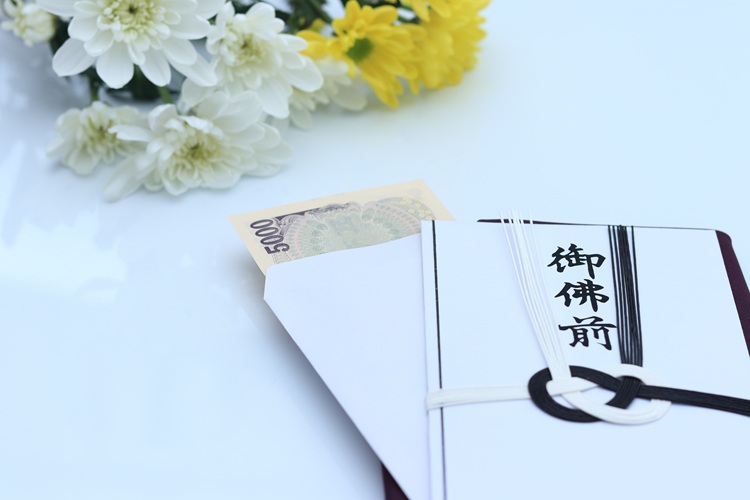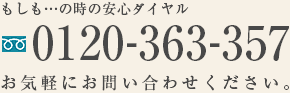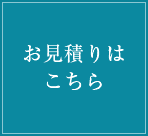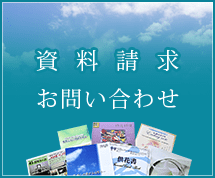知識
公開日 │ 2024年04月30日
更新日 │ 2026年02月09日
急逝と逝去の違いとは?身内が急に亡くなった際の対応や流れを詳しく解説
もくじ

いずれの言葉においても、実際に使われる場面や受け取る側のニュアンスが微妙に異なるため、それぞれの違いをしっかりと理解しておくことが大切です。そこで今回は急逝と逝去の言葉の違いから、近しい類義語との比較や使い分けに至るまで詳しくご紹介いたします。
他にも、身内が急に亡くなった際にするべきことや訃報を知らせるまでの流れ、また、そうした連絡を受けた際の適切な対応についても解説をいたします。
1.急逝と逝去、死去の違いについて
急逝とは、元気な方が何の前触れもなく突然亡くなることを指します。そのため、軽症だと診断されていた方の病状が突然悪化して死に至った場合や、自身で命を絶ってしまった場合などに使われるのが一般的です。
【例文】
- 実家の父の急逝に伴い、家業を継ぐことになった。
- 映画撮影中の俳優が急逝したとニュースで報じられた。
一方の逝去は死去という用語の尊敬語にあたるもので、亡くなった事実を言い表す際の丁寧な表現として使用される言葉になります。
これは例えば自身の身内以外の方向けに、亡くなったことを発信する場面で耳にする機会も多いでしょう。
【例文】
- 御母堂様のご逝去の報に接し、心からご冥福をお祈りいたします。
(弔電文の一例) - かねてより闘病中だった〇〇さんが昨日ご逝去されました。
なお死去に関しては直接的な表現であるがゆえに、遺族に向けた表現として用いるものではありません。そのため、自身の家族や所属している会社の関係者(社長・上司・部下など)が亡くなった際に使うようにします。
【例文】
- 弊社の代表取締役である〇〇が死去した事実をご報告いたします。
逝去と死去という言葉を適切に使い分けることは、関係者や遺族に対しての敬意を表す上で大切なマナーとなります。
間違った表現を使う事で受け取る側の感情を大きく損ねてしまう可能性もあるため、違いをしっかりと理解した上で正しく使い分けをしましょう。
2.急逝と近しい言葉とその使い方
急逝という言葉以外にも、人が亡くなったことを表す用語がいくつか存在しています。それぞれ使用される場面や伝わるニュアンスなどが異なるため、具体的な例文も挙げつつご紹介をいたします。
2-1.急死、即死
急死や即死は、急逝と同様に人が急に亡くなることを示す言葉です。違いとしては急死や即死が「死」という文字が含まれていることもあり、改まった場で使用することが避けられるのに対し、急逝は丁寧な表現で言い表す際に用いられます。
また、交通事故や自然災害といった突発的な原因で亡くなった際に急死と表現することがよくあります。
【例文】
- 昨晩起きた衝突事故で〇〇さんが急死した。
- 細かい要因は分からないが、医師によると即死だったことが確認された。
2-2.他界
他界は今生きている世界(この世)とは別にある世界(あの世)に行くことを意味する言葉です。突然の死を意味する急逝や急死とは異なり、死去や逝去といった用語と同じように使用されます。
ただし、仏教的なニュアンスが含まれているというのもあり、神道やキリスト教では基本的に他界という言葉が用いられることはありません。
また同じ仏教であっても、他宗派とは異なる考えを持つ浄土真宗では他界という表現が好ましくないため、使用する際は注意が必要です。
【例文】
- 昨年10月に私の祖母が享年〇歳で他界しました。
2-3.永眠
永眠は字の通り、亡くなったことを永遠の眠りに例えて言い表した言葉です。眠るという表現になっているため、死という言葉のネガティブな印象が薄れることもあり、葬儀の事後通知や喪中ハガキの文面などに多く使用されています。
【例文】
- 去る◯月◯日、父〇〇が永眠したことを報告します。
3.身内が急に亡くなった場合の流れ
身内が急に亡くなるという状況では誰しもが動揺して、冷静ではいられなくなってしまうことが想定されます。そのため、もしもの際に備えて予め大まかな流れを理解しておくことが大切です。
ここでは自宅と病院とで急逝した際の対応についてそれぞれ順に見ていきましょう。
3-1.自宅で亡くなったケース

自宅で急に亡くなった場合は、状況に応じて対応が異なります。元々持病があって自宅での療養をされていた方であれば、まずはかかりつけの医師に連絡をするようにしましょう。
その時点で葬儀社が決まっている際は予め連絡をしても構いませんが、医師が到着して死亡診断書を発行するまではお身体の移動やドライアイスの処置などを依頼することは出来ないため、注意が必要です。
自宅で普段通りに生活していたのにも関わらず、気付いたら息をしていなかったという状況であれば、蘇生の可能性もあるため、まずは救急車を呼びましょう。その後は病院に搬送されるか、亡くなったことが明らかな場合は現場の救急隊の判断で警察に連絡が入ります。
警察の対応になった際は、自宅での現場検証や事情聴取がおこなわれ、故人は警察署に搬送されることとなります。死因の特定をする過程で解剖がおこなわれるケースもありますが、事件性がないと判断されれば死体検案書が発行されます。
いずれの場合においても警察の担当者とのやり取りの中で都度状況が伝えられるため、頃合いを見て葬儀社の手配をおこなうようにしましょう。
もしかかりつけ医がいるのに慌てて救急車を呼んでしまった場合には、突然死と同様に警察の介入が発生する可能性もあります。
結果として本来する必要のない現場検証や事情聴取、警察署への往訪などの対応を余儀なくされることもあるため、もしもの際の医師の連絡先などを家族間で事前にしっかりと共有しておくことも大切です。
関連記事
3-2.病院で亡くなったケース

病院で急逝した場合は事件性がない限り、その場で医師が死亡診断書を発行してくれます。医師からは葬儀社への連絡をするように言われますが、大きな病院などでは院内にある霊安室へ一時的に身体を安置する場合もあります。
その後は葬儀社の手配するお迎えの車で自宅や専用の安置施設へと移動する流れとなるでしょう。
4.急逝時の連絡手段や伝える順番について
身内が急逝した際には亡くなったという事実を告げる訃報を親族や友人関係に知らせていく必要があります。その際の連絡手段や伝える順番について詳しくご紹介をいたします。
4-1.連絡手段は電話やメールを状況に応じて使い分ける
身内の訃報は緊急度の高い連絡事項となるため、すぐに知らせをする場合には必ず電話で伝えるようにしましょう。連絡をした際、特に急に亡くなったような状況では経緯や葬儀のことなどを事細かに聞かれることもあります。
ですが、自身もショックが大きく、動揺してしっかりとした内容を伝えられない可能性もあるため、詳しいことは少し気持ちが落ち着いてから再度連絡する旨を伝えるのも1つの方法です。
また、深夜・早朝の時間帯や相手方の都合が悪い場合は取り急ぎメールで一報を入れるなど、状況に応じた使い分けをされるとよいでしょう。
4-2.亡くなった事実は故人と近しい関係から順に伝える
取り急ぎ訃報の連絡をするのは、故人のお連れ合いやその子供、孫にあたるような近しい方々にしていきます。
その他に親戚や故人の友人関係など、各方面に声を掛けることもあるかもしれませんが、亡くなったばかりのタイミングで連絡を広めてしまうと、病院や自宅に大勢駆けつけて身動きが取れなくなることも想定されます。
そのため、近しい関係以外には、ある程度葬儀の段取りがついた後で伝えていくことをおすすめいたします。
5.急逝の連絡を受けた場合の対応は?

急な知らせを告げられた際には、連絡を受け取った側も動揺してしまい、どんな言葉をかけてよいか分からなくなってしまうこともあるでしょう。
また、つい気持ちだけが先走ってしまい、遺族に対して失礼にあたる言動をしてしまう可能性もあります。
そうした事態を避けるためにも、急逝の連絡を受けた場合の対応や流れについて最後にご紹介いたします。
5-1.お悔やみの言葉を述べる
故人の家族から急逝の連絡を受けた際はあまり長々と話をすることは却って負担となる可能性があります。そのため、
- 「心からお悔やみ申し上げます」
- 「この度はご愁傷さまです」
といったお悔やみの言葉を簡潔に述べるのがよいでしょう。
また、一般的なマナーとして「度々・ますます・返す返す」といった重ね言葉や、「死」に関する直接的な表現を用いることは避ける必要があるため注意が必要です。
5-2.葬儀の日時を確認する
急に亡くなったような状況では、相手方も慌てていて葬儀に関する詳細が聞けないこともあるでしょう。その際は無理に詳細を聞かずに、落ち着いてから連絡をしてもらう配慮も必要になってきます。
もし再度連絡があった際には葬儀の日時・形式・場所などをしっかりと確認して、参列ができるかどうかの返事をするようにしましょう。
また、葬儀までの日程が空く場合に、自宅や安置施設で故人と会いたいといった希望がある場合には、事前に家族へ伝えた上で判断を委ねるようにします。
急逝は突然亡くなること、逝去は亡くなったことを丁寧な表現で言い表した言葉(まとめ)
急逝は元気な方が何の前触れもなく亡くなることをいい、逝去は亡くなったことを表す際の丁寧な表現として用いられるものです。
急逝と似た言葉で急死や即死といった表現がありますが、「死」という言葉が含まれているため会話上で使われることはほとんどありません。
他に逝去と似た意味の言葉としては他界や永眠といったものが挙げられますが、これらは亡くなった事実を柔らかい表現で置き換えることが出来るため、使用される場面も多くあります。
身内が急逝した際は心情としても大変辛く、つい慌ててしまうことも想定されますが、まずは落ち着いて葬儀社の手配から進めていくことが大切です。
また、自身が急逝の知らせを受けた際には遺族の心情を慮り、まずは心からのお悔やみの言葉を述べて、出来うる限りのサポートを申し出るようにしましょう。