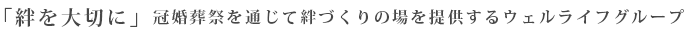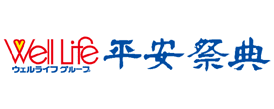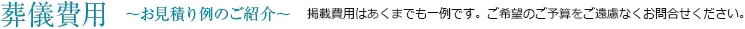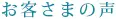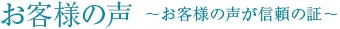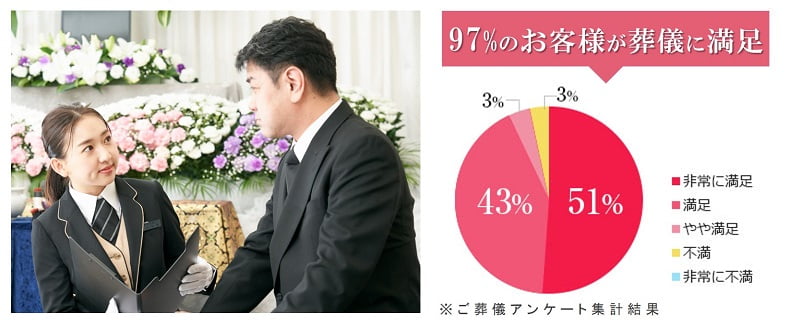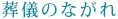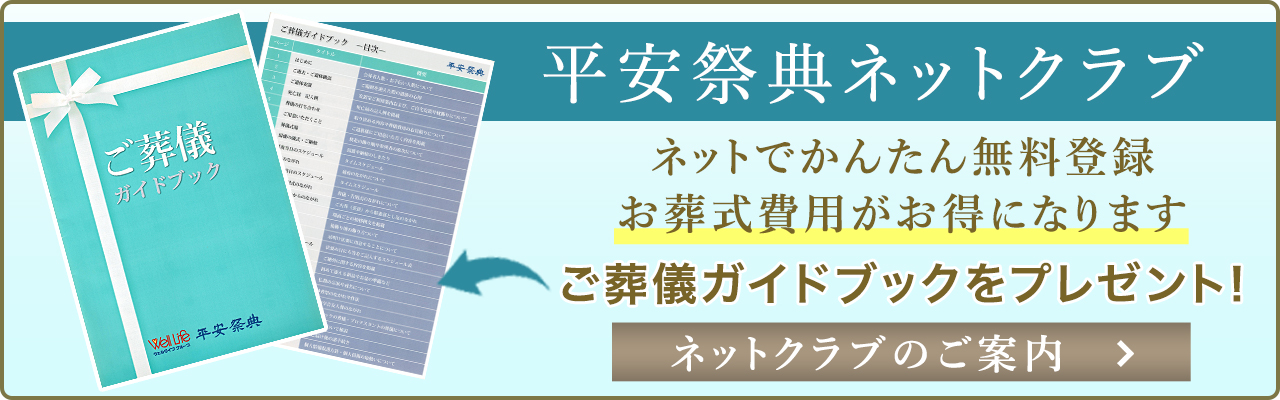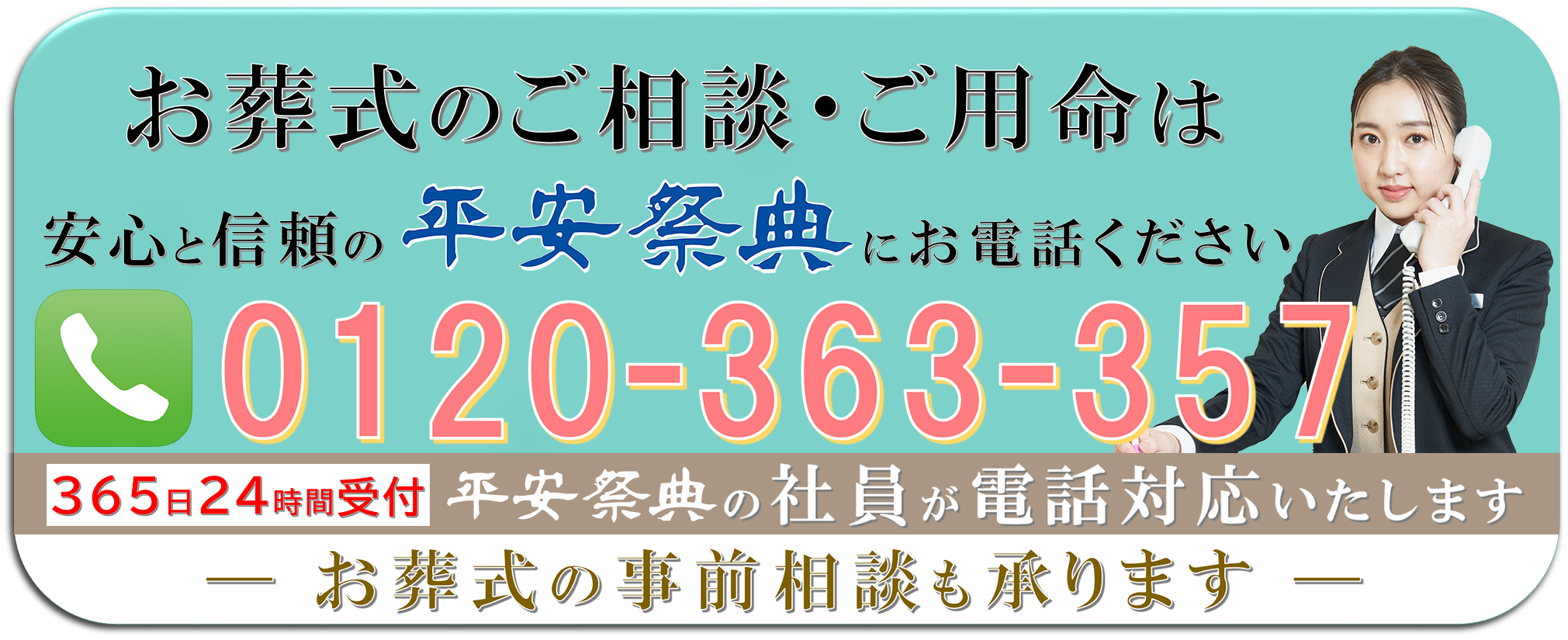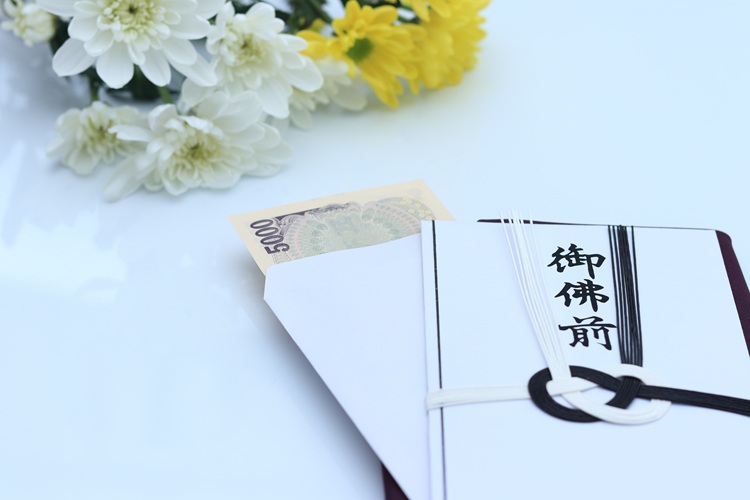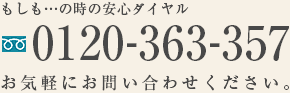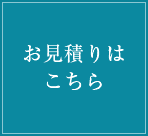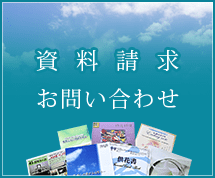準備
公開日 │ 2025年02月28日
更新日 │ 2025年03月07日
老衰とは?老衰死の前兆やご家族が老衰死に備えてできること
もくじ

老衰死には、前兆があります。ご家族に老衰の前兆が表れたら、落ち着いて対処することが大切です。今回は、老衰について解説します。老衰死の前兆やご家族が老衰死に備えてできることを解説するため、ご参考になさってください。
1.老衰とは
老衰とは、高齢となり年齢を重ねた結果、自然と心身の機能が衰えた状態を指します。 老衰死は自然死であり、現代では高齢化や医療科学の進歩により、死因の上位に位置しています。
1-1.老衰死の定義は何歳から?
老衰死の年齢に、明確な定義はありません。 しかし、一般的には平均寿命を超えた年齢で病気や事故などではなく、加齢によって心身の機能が徐々に衰えていった場合に、老衰と判断します。
厚生労働省の「令和5年簡易生命表の概況」によると、2023年の日本人の平均寿命は以下となっています。”令和5年簡易生命表によると、男の平均寿命(0歳の平均余命のこと。以下同じ。)は81.09年、女の 平均寿命は87.14年となり前年と比較して男は0.04年、女は0.05年上回っている。”
引用元:令和5年簡易生命表の概況 (https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life23/dl/life23-15.pdf)
80〜90歳前後での自然死が、老衰死と判断されると考えてよいでしょう。
1-2.老衰の症状が改善されることはある?
老衰の症状には、筋肉や握力の低下、歩行速度の低下、平衡感覚の低下などがあります。食事に対する関心が薄れ、脳機能の低下によって睡眠時間が増加します。このような老衰の症状が表れると、基本的には症状が改善されることはありません。
老衰は病気ではなく、加齢に伴う自然な心身の変化であるからです。ただし、老衰には「中治り現象」というものがあります。中治り現象とは、命の灯火が消えかかっている際に、一時的に元気になることです。
理由は諸説ありますが、脳が寿命を延ばそうとして、アドレナリンなどの神経物質を分泌するからではないかといわれています。中治り現象が表れると老衰から復活したような印象を受けますが、あくまで一時的な現象である点に留意しましょう。
2.老衰死の前兆
老衰死には、体重の減少など前兆があります。睡眠時間の増加や身体機能の急激な低下も、老衰死の代表的な前兆です。
老衰死の前兆について詳しく解説します。
2-1.体重の減少
老衰になると、内臓機能が低下します。 食事をするのが難しくなるため、体重の減少が著しくなります。食事ができていたとしても、 体重の減少が進むことがあります。老衰が進むと、摂取した栄養が吸収されにくくなるからです。食事をするのが難しい場合は、流動食に切り替えたり、点滴での栄養補給を検討したり、医師の判断に委ねることが大切です。
2-2.睡眠時間の増加
老衰になると、心身の機能が徐々に低下していきます。脳機能も低下するため、意識を保つのが困難になってしまうのです。日中の睡眠時間が著しく増加した場合、老衰死の前兆の可能性があります。 睡眠時間の増加は老衰の代表的な症状の一つであるため、無理に起こそうとせず、自然な流れに沿ったケアをおこなうようにしましょう。
2-3.身体機能の急激な低下
老衰になると、身体機能が急激に低下し、日常生活に支障をきたすようになります。具体的には、以下のような症状が多く見受けられます。
- 筋肉や握力が低下し物を握れなくなる
- 歩行速度が低下し歩くのが困難になる
- 平衡感覚が低下しよろめくようになる
- 体温が低下し身体が常に冷えた状態になる
- 意識が混濁し不自然な言動が増える
これまでできていたことが徐々にできなくなっていくのが、老衰の症状です。自然に身を任せながらも、必要なサポートやケアをおこない、焦らずに見守るようにしましょう。
3.ご家族が老衰死に備えてできること
ご家族が老衰死に備えてできることは、落ち着いて心の準備をすることです。老衰死は自然死であることを理解し、ご本人の尊厳を保てるよう見守ることが大切です。また、ご家族は現実的な問題にも立ち向かわなくてはなりません。
葬儀やお墓について話し合う、ご本人に延命治療の意思を確認する、遺言書の準備を進める、など、老衰死に備えてするべきことがあります。ご家族が老衰死に備えてできることを詳しく解説します。
3-1.葬儀やお墓について話し合う
ご家族の老衰死に備えて、葬儀やお墓について話し合い、方針を決定しましょう。可能であれば、ご本人の意思を確認し、尊重します。ご本人と意思疎通をするのが難しい場合は、過去の意思を確認したり、エンディングノートを参考にしたり、手がかりを探します。
ご本人の意思を尊重したうえで、ご家族で葬儀やお墓をどのように執り行うか、具体的に決定する必要があります。不明点があれば葬儀社などに相談し、葬儀やお墓の生前契約を進めることも選択肢の一つです。
関連記事
3-2.ご本人に延命治療の意思を確認する
老衰を迎えてから、容態が急変することがあります。万が一のことがあった場合に、延命治療を希望するか、可能であればご本人に意思を確認しましょう。
ご本人が事前に書面(リビング・ウィル)で延命治療に関する意思表示をしている場合は、その意思が尊重されます。ご本人と意思疎通をするのが難しい場合は、ご家族で話し合い、延命治療に関して判断をします。医師の判断や意向を聞き、医学的な観点からも検討することが大切です。
3-3.遺言書の準備を進める
老衰が進む前に、可能であればご本人に遺言書の準備を進めてもらいましょう。
ただし、遺言書には法的な決まりがあります。決まりを守った正式な遺言書でなければ、ご本人が作成しても法的な効力を持ちません。
老衰が進行し、ご本人が遺言書を作成するのが難しい場合は、臨終遺言という形式にする手段があります。
臨終遺言とは、病気や事故、老衰などで命の危険が迫っている場合に作成する遺言書のことです。
ご本人から遺言の内容を聞いた証人が、遺言書を作成できます。
臨終遺言を作成するためには、3人以上の証人が必要となるなど、条件がいくつかあります。遺言書の準備は必要に応じて行政書士や弁護士など専門家に相談しながら、慎重に進めるようにしましょう。
老衰とは加齢によって心身の機能が徐々に衰えていく状態のこと(まとめ)
老衰とは、病気や事故などではなく、加齢によって心身の機能が衰弱していく状態のことです。年齢に定義はありませんが、一般的には平均寿命の80〜90歳を超えて、加齢によって心身の機能が徐々に衰えていった場合に老衰と判断されます。
老衰が進行してご逝去すると、「老衰死」を迎えたことになります。老衰になると、筋肉や握力の低下、歩行速度の低下、平衡感覚の低下などの症状が表れます。ご逝去される直前には、前兆として体重の減少、睡眠時間の増加、身体機能の急激な低下などがみられることもあります。
ご家族は老衰死に備えて落ち着いて心の準備をし、葬儀やお墓、延命治療、遺言書についてなど、現実的な問題に対処できるよう努めましょう。