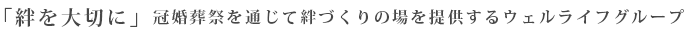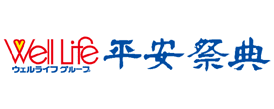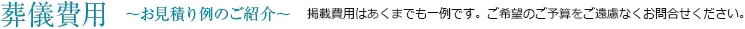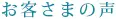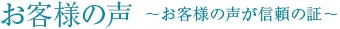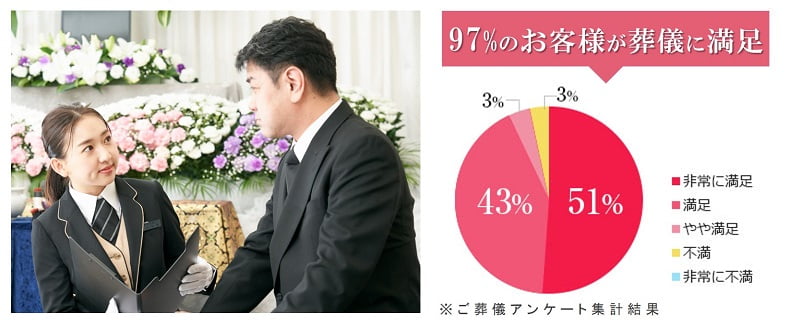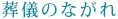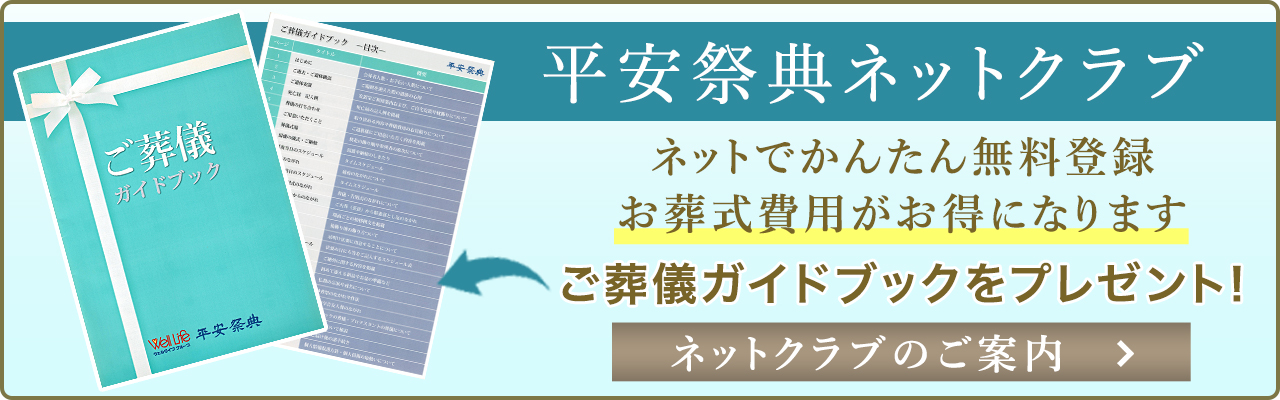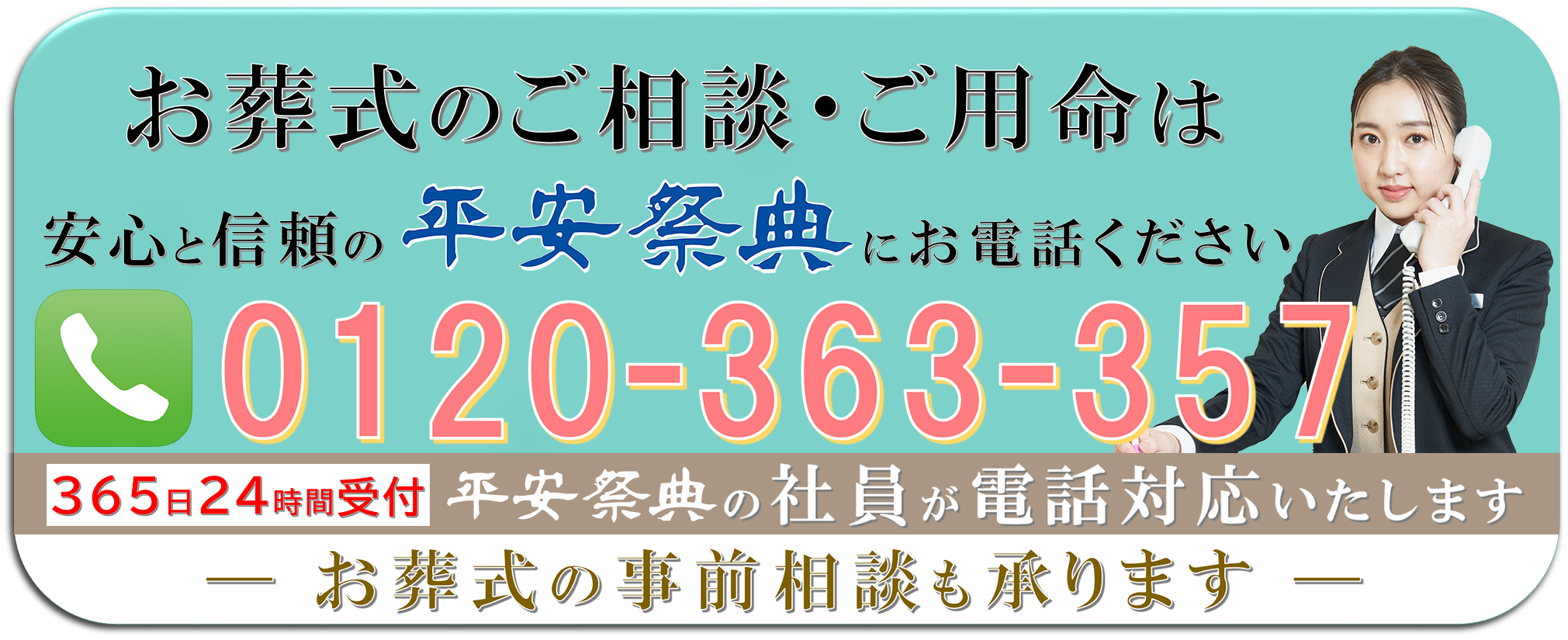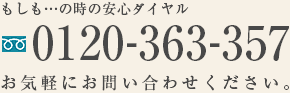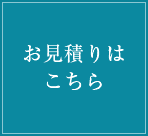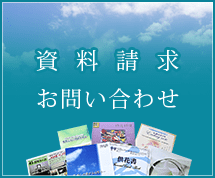マナー
公開日 │ 2025年11月13日
「お悔やみ申し上げます」の正しい使い方・使ってはいけない場面
もくじ

1.「お悔やみ申し上げます」の言葉が持つ意味
「お悔やみ申し上げます」の「お悔やみ」という言葉には、「人の死を弔い悲しむ」という意味があります。「申し上げます」は謙譲語であり、とても丁寧な敬語表現です。したがって、「お悔やみ申し上げます」という言葉は、「故人様の死を弔い、心から悲しんでいます」という、故人様への弔意と、ご遺族への哀悼の意を表す丁寧な表現になります。
この言葉は、葬儀や弔問時、訃報を受けた際のご遺族に対するお声かけや挨拶として、最もふさわしい表現の一つです。故人様とご遺族に最大限の敬意と弔意を込めて、落ち着いた声のトーンで、ゆっくりと丁寧にお伝えしましょう。
2.「お悔やみ申し上げます」を使う場面
「お悔やみ申し上げます」を使う主な場面は、葬儀や弔電、弔問時です。メールやLINEなど、文面で使っても構いません。 「お悔やみ申し上げます」を使う場面について詳しく解説します。
2-1.葬儀
葬儀や告別式の受付では、「この度はご愁傷様でございます。心からお悔やみ申し上げます。」と挨拶するのが一般的です。葬儀でご遺族にお声かけする際も、同じように挨拶しましょう。ご遺族は悲しみの中、慌ただしく葬儀を進められます。 葬儀でのお声かけや挨拶は簡潔に、かつ真心を込めて弔意を表明することが大切です。
2-2.弔電
弔電とは、葬儀に参列できない場合に、弔意を伝えるために送る電報のことです。一般的な弔電の文章例は、以下のとおりです。「○○(故人様のお名前)様のご逝去を悼み 心よりお悔やみ申し上げます」 弔電は、20~80文字程度で短くまとめます。 句読点は「区切り」や「終わり」を意味するため、使わないのがマナーです。
「重ね重ね」や「追って」などの忌み言葉も、使わないように配慮しましょう。
2-3.弔問
弔問とは、お通夜や葬儀以外の日に、ご自宅へ訪問して弔意を伝えることです。弔問時は、ご遺族に対して「この度は誠にご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。」などとお伝えします。ご遺族への挨拶を済ませてから、故人様の霊前に手を合わせ、焼香しましょう。事前にご遺族に弔問の予定などを連絡する際も、同じように挨拶するのが一般的です。
2-4.メールやLINE
近年では、メールやLINEでの訃報連絡が増えています。メールやLINEなどのSNSを通じて訃報を受け取った際の返信例文は、以下のとおりです。
「この度は〇〇(故人様のお名前)様の突然の訃報に驚いております ご逝去を悼み 心よりお悔やみを申し上げます」 返信は短く簡潔にまとめ、句読点や絵文字は使わないようにしましょう。
ただし、メールやLINEでの連絡は弔事において、あくまで略式です。本来、弔事に関する連絡は、口頭や書面で行うのが一般的なマナーです。
略式であるメールやLINEでの連絡や返信は、親しい関係性や緊急性がある場合に限定しましょう。文末に「返信には及びません」といった一言を添えると、ご遺族の負担を軽減できます。
3.「お悔やみ申し上げます」を使ってはいけない場面
「お悔やみ申し上げます」という言葉には、故人様のご逝去を悼む弔意が込められています。弔事にふさわしい言葉ですが、四十九日以降は使わないのが一般的です。仏教において四十九日は、故人様が成仏し喪が明ける「忌明け」を意味するからです。
一周忌や三回忌など、四十九日以降の法要では、「お悔やみ申し上げます」という言葉に代わって、「心より哀悼の意を表します」や「ご冥福をお祈りします」などと述べましょう。ただし、仏教ではなく、神道やキリスト教などの場合は、「ご愁傷様」や「ご冥福」などの言葉は使えません。
「◯◯(故人様のお名前)様の安らかな眠りをお祈りします」などと挨拶します。
弔事での言葉のマナーは、宗教や宗派によっても異なる点に留意しましょう。
4.「お悔やみ申し上げます」と併用する言葉
「お悔やみ申し上げます」という言葉は単独でも使えますが、他の表現と併用して言葉を添えることで、より深い弔意を表明できます。
最も併用されることが多い言葉は、「ご愁傷様でございます」という表現です。「ご愁傷様」には、「あなたの深い悲しみに寄り添います」という意味があります。「お悔やみ申し上げます」の前に添えることで、よりご遺族に寄り添った、丁寧な表現として弔意を伝えられるでしょう。
他にも、「誠に残念でなりません」や「ご冥福をお祈りします」といった言葉を添えることもできます。
5.「お悔やみ申し上げます」の返答
ご遺族が参列者から「お悔やみ申し上げます」と挨拶された際は、「恐れ入ります。お気遣いありがとうございます。」などと返答するのが一般的です。
「お忙しい中、ありがとうございます」と添えるのも良いでしょう。ただし、葬儀の受付などでは、「恐れ入ります」の一言で返答しても構いません。弔意を表明していただいた際の返答では、簡潔に感謝の気持ちを伝えることが大切です。
無理に、故人様のお話を始める必要はありません。参列者への感謝の気持ちを込めて、忌み言葉などに配慮しながら、落ち着いた対応を心がけましょう。
「お悔やみ申し上げます」は弔意を表す大切な言葉(まとめ)
「お悔やみ申し上げます」は、故人様のご逝去を悼み、ご遺族に心からの哀悼の意を伝える、丁寧な弔意の表現です。この言葉は、お通夜・葬儀・弔問時といった場面だけでなく、メールやLINEによる略式の連絡でも使用されます。
ただし、弔電や文面では、句読点を控えるなど、マナーに配慮することが大切です。使用する時期としては、故人様の成仏をもって喪が明ける、四十九日の忌明けまでが一般的です。忌明け後は、「心より哀悼の意を表します」などと挨拶します。
ご遺族に対して「お悔やみ申し上げます」とお声かけする際は、先に「この度はご愁傷様でございます」などとお伝えし、弔意を丁寧に表明できるよう、心を込めましょう。