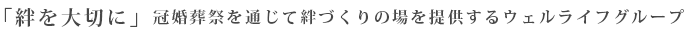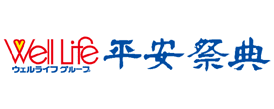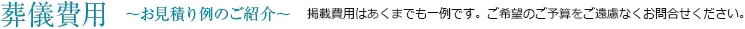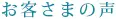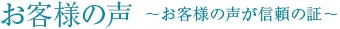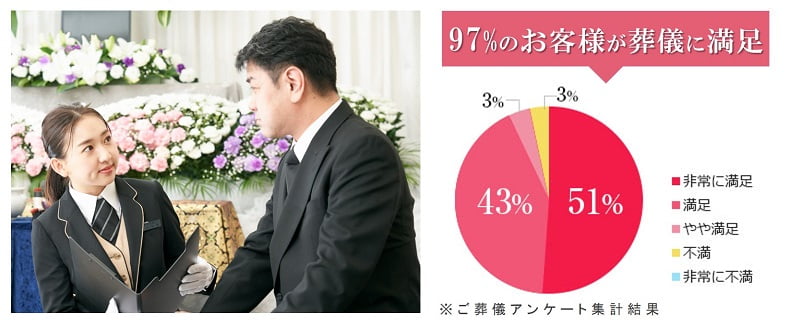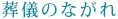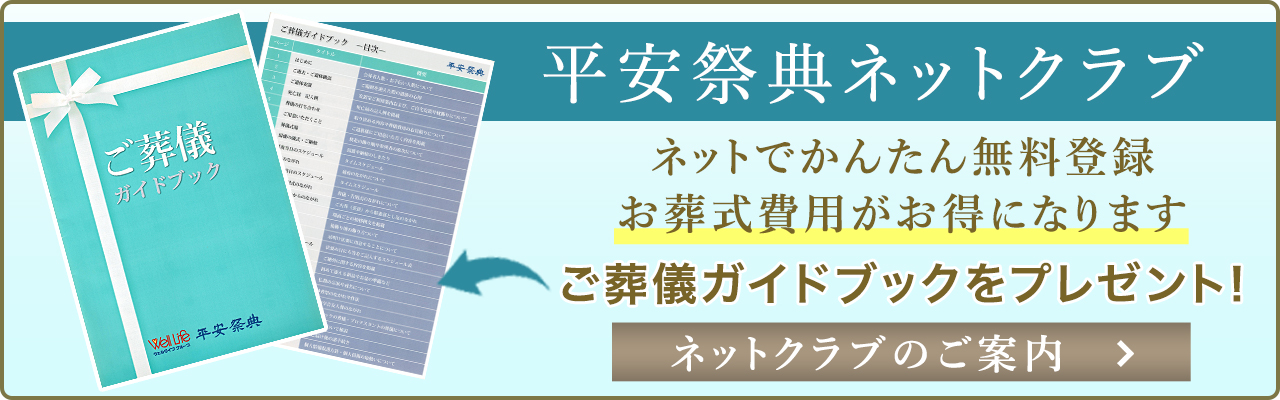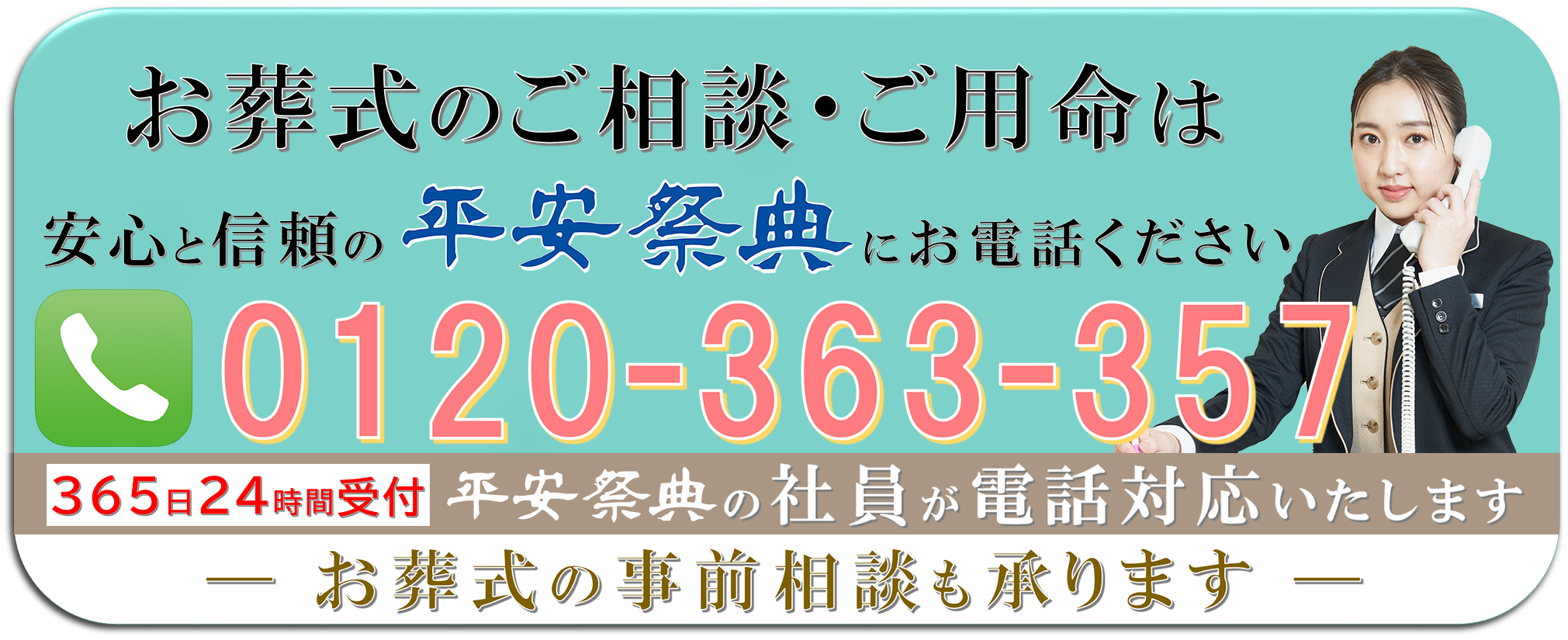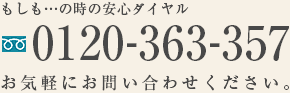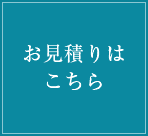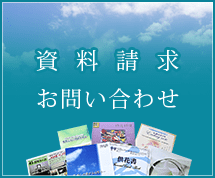手順
公開日 │ 2021年10月14日
更新日 │ 2024年06月04日
焼香のやり方とは?正しい作法や気をつけるべきマナーを解説

中には他の方のお焼香の作法を見て、その場で同じように振る舞って真似をする方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、周りには分からないかも知れませんが、多くの方の視線が集まる遺族の立場では中々そうもいきません。
そのため、社会人としてなるべくなら事前にお焼香のマナーを心得ておきたいものです。
そこでまずはお焼香の意味を十分に理解して、実際の流れや手順をしっかりと把握できるように順番に内容を解説させていただきます。
1.お焼香とは?
お焼香とは葬儀や法事の際に、香炉の中に置かれた香炭へ「抹香」と呼ばれる木片などをくべることで、故人や仏様に対して拝む作法のことをさします。その目的としては、「香り」や「煙」を生じさせることが挙げられ、それぞれに意味があるため順番に見ていきましょう。
1-1.お焼香の意味について
お焼香をする意味は大きく分けて三つにまとめられます。
- 故人や仏様へのお供え
お供えというと、お花や食べ物、飲み物などを想像されるかもしれませんが、実はお焼香の「香り」も敬いの心をあらわすものとされています。 - 自身と周りの空間を清浄にするため
お参りをする場所は、故人を送り出す空間でもあり、仏様をお迎えをする場所でもあります。そのためお香を焚いた時に生じる「香り」や「煙」によって、自身と周りの空間を清める意味があります。 - 香りにより自身の気持ちを鎮めるため
現代でも自宅などでリラックス効果を得るために、お香を焚く方もいらっしゃいますが、同じようにお焼香も「香り」によって心身を清め、真摯な心持ちでお参りができるようになるという意味があります。
1-2.お線香との違い
お線香は15センチほどの長さで棒状になっており、先端に火をつけてお参りをするために使用するものになります。実はお焼香はお線香を細かくしたものを使用しているため、「煙」や「香り」を生じさせてお参りをするという点で、両方とも意味合いに変わりはありません。
ただし、お参りで使用される場面に違いが見られます。式の開式前まではお線香を使用してお参りをしますが、法要や葬儀の式中などではお焼香でのお参りをすることが一般的です。
またお線香は日常的に自宅で仏壇にお参りをする際や、お墓参りに訪れた際に使用することが多いです。
1-3.お香典にも関係がある
昔は葬儀の際に大量のお香を必要としていたため、参列者がこぞってお香を持ち寄っていました。ですが、江戸時代に入ってお線香が広まるようになると、大量のお香は必要なくなったため、その代わりに金品を持ち寄るようになったことが、お香典の由来とも言われています。
2.お焼香の流れ
2-1.宗派ごとに違うお焼香のやり方
実は宗派によって、細かくお焼香の回数が定められています。ですが、参列した先の宗派が分からない場合などもありますので、特に指定されない限りは自身の家の宗派に沿った形式でお焼香をしても問題ないとされています。
- 真言宗
抹香を額の高さに掲げておしいただき、焼香は3回おこなう。 - 浄土宗
抹香を額の高さに掲げておしいただき、焼香は1〜3回おこなう。 - 浄土真宗
本願寺派(西)は抹香を額におしいただかず、そのまま1回焼香する。大谷派(東)は抹香を額におしいただかず、そのまま2回焼香する。 - 日蓮宗
抹香を額の高さに掲げておしいただき、焼香は1〜3回おこなう。 - 臨済宗
1回目は抹香を額の高さに掲げておしいただき、2回目はそのままの状態で焼香する。 - 曹洞宗
1回目は抹香を額の高さに掲げておしいただき、2回目はそのままの状態で焼香する。 - 天台宗
抹香を額の高さに掲げておしいただき、焼香は3回おこなう。
3.お焼香は主に3つの形式でおこなわれる
お焼香は基本的に故人との関係が近い方から順番におこないます。そのため、喪主が1番始めにお焼香をして、後から遺族、親戚、参列者と続いていきます。式場内ではあらかじめ席次が決められているので、スタッフから声をかけられて順番に案内をされますが、式の規模によっては2人〜3人同時にお焼香をおこなう場合があります。
なお、お焼香は主に以下の3つの形式でおこなわれるため、それぞれ順番にご紹介をさせていただきます。
3-1.立礼焼香

椅子の席が用意されている式場などでは一般的に立礼焼香でのご案内となります。これは文字通り、一度席から立ってお焼香をおこなう形式です。
親族は僧侶の席の手前、参列者は遺族席の手前にそれぞれ焼香台が設置されているので、自身の順番が回ってきたら席から立ち上がって焼香台へ向かい、その場で立ったままお焼香をおこないます。
- スタッフより声が掛かってから焼香台の前に進み、まずは遺族に一礼します。
- 祭壇上の遺影を見て再度一礼をします。
- 宗派に応じた焼香作法に則り、抹香(まっこう)を右手でつまみます。
- 左側に置いてある香炉の中へ抹香を落とします(1回〜3回)。
- 改めて祭壇上の遺影に向かって一礼します。
- 最後に遺族へ一礼をしてから自身の席へと戻ります。
3-2.まわし焼香

まわし焼香は着席した参列者の席に香炉を廻し、順次お焼香していただく形式です。中でも、座礼用の焼香台を置くことが難しい場合などに取られる方法でもあります。
お焼香用の香炉と抹香が一緒にお盆に乗せられた状態で順番に手元へ回ってきます。隣の人から回ってきたら、その場で軽く会釈しながら両手で受け取るようにしましょう。お焼香を終えた後は、また次の方へ香炉と抹香をセットでお渡しをします。
- 手元に香炉が回ってきたら、軽く会釈をしてから両手で受け取ります。
- 香炉を自分の目の前に置き、祭壇上の遺影に向かって合掌します。
- 宗派に応じた焼香作法に則り、抹香(まっこう)を右手でつまみます。
- 左側に置いてある香炉の中へ抹香を落とします(1回〜3回)。
- その場で合掌してから、再度祭壇上の遺影に一礼します。
- お隣に座っている方に香炉を回します。
3-3.座礼焼香

座礼焼香も文字通り、座った状態でのお焼香をおこなう形式です。自宅や寺院の和室などでお葬式を執り行う場合などに用いられます。基本的には僧侶が着座している手前に低めの焼香台が設定されているため、自身の順番が回ってきたら中腰の状態で移動して焼香台へ向かい、その場で座ったままお焼香をおこないます。
- 焼香の順番が来てから中腰の姿勢で正面へと進みます。
- 焼香台の手前に座り、遺族に一礼します。
- 祭壇上の遺影に向かって一礼します。
- 宗派に応じた焼香作法に則り、抹香(まっこう)を右手でつまみます。
- 左側に置いてある香炉の中へ抹香を落とします(1回〜3回)。
- 改めて祭壇上の遺影に向かって一礼します。
- 焼香台前から下がり、遺族に一礼してから席に戻ります。
4.気をつけるべき焼香マナー
4-1.なるべく数珠を持参する
お焼香をする際には必須ではないものの、社会人として数珠を手元に持っておくことがマナーとされています。数珠には、大きく分けて略式数珠と本式数珠と2種類あります。

略式数珠は一重になっており、どの宗派でも共通して使用できるもので、5000円〜1万円程度が相場です。本式数珠は各宗派ごとに決められた形状になっており、108個の玉数が付いています。こちらは仏具としてより本格的な仕様となっているため、選ぶ際は1万~3万円程度が相場です。
お葬式に参列する際はどちらを持参しても問題ありませんが、初めて購入される方はまず略式数で用意することをおすすめいたします。なお、お焼香の直前になって数珠の貸し借りをされる方もいらっしゃいますが、これは明らかなマナー違反です。
なぜなら数珠は、使用者本人の分身でありお守りでもあるものなので、たとえ親族間や友人間であっても数珠の貸し借りは必ず避けるようにしましょう。
以下では参考までに、宗派ごとに異なる数珠の持ち方をご紹介いたします。
- 真言宗
両手の中指でお念珠を掛け、親玉が上になるように二重に巻きます。房は親指の内側に垂らして持つようにしましょう。 - 浄土宗
親玉を揃えて、親指で押さえるように握る。その際に房を手前側に下げるようにします。 - 浄土真宗
二重にした念珠を両手にかけて持ち、房は下に垂らすようにします。 - 日蓮宗
念珠の輪を八の字に捩じって中指にかける。右手側に2本の房、左手側に3本の房が来るように持ちます。 - 臨済宗
念珠を二重にして、左手だけに掛かるように握ります。 - 曹洞宗
念珠を二重にして、左手だけに掛かるように握ります。 - 天台宗
念珠を人差し指と中指の間に掛けて、そのまま合掌するように握ります。
房は自然に下側へ垂らすようにしましょう。
4-2.手荷物は少なめに
お焼香をする際には両手で合掌をするため、あまりたくさんの手荷物を持っていると、その荷物の置き場に困ってしまいます。式場によっては焼香台の手前に荷物を置く専用の台が用意されていることもありますが、参列する際には小さめのカバンに必要最低限の物だけを入れて手荷物を持参するように心がけましょう。
4-3.喪主や遺族に対しての挨拶
式場で喪主や遺族と顔を合わせた際には、まずお悔やみの言葉を述べます。その際にはあまり難しい言い回しなどはせずに、「この度は誠にご愁傷様です。」と一言添えて挨拶をされるとよいでしょう。
なお、葬儀の場においては不幸が続くことをイメージさせる重ね言葉を避ける必要があります。そのため、 重ね重ね、またまた、たびたび、といった言葉を使用してお悔やみを伝えるのは避けるようにしましょう。
4-4.参列時の服装や身だしなみについて

葬儀に参列される際は、基本的にブラックフォーマルのスーツや喪服を着用するようにします。また、女性については黒の肌の露出が少ないワンピースやスーツ、アンサンブルの着用が望ましいです。
なお、お通夜に関しては訃報を聞きつけてから急いで駆け付けたという姿勢を示すために、平服での参列でも問題はないとされています。ただし、赤色などの派手な配色の服装は避けるようにして、アクセサリーも必要最低限のものを身に着けるなど多少の配慮は必要です。
遺族の立場から見て、参列者の身だしなみは意外と気になってしまうものです。喪服と平服のいずれの場合においても、シワや汚れが付いていない清潔感の感じられる装いを意識して参列するようにしましょう。
葬儀におけるお焼香の正しいやり方を解説(まとめ)
お焼香という行為は仏式のお葬式で特に「煙」と「香り」を生じさせることによって、仏様へのお供えだけでなく、周りの空間や自分自身を清めるといった重要な意味を持つものです。また、お焼香の作法として、宗派ごとにお焼香をする回数が1〜3回でそれぞれ異なり、額におしいただくものと、そうでないものとに分けられます。
自身の宗派ではどのようにお焼香をすればよいのか、お葬式に参列をする前にしっかりと把握しておくようにしましょう。
さらに式場では、立礼焼香・座礼焼香・まわし焼香など、お焼香へのご案内のされ方も異なる場合があります。それぞれの場面において、お焼香の流れや作法が少しずつ異なりますので、合わせて知っておくと安心です。